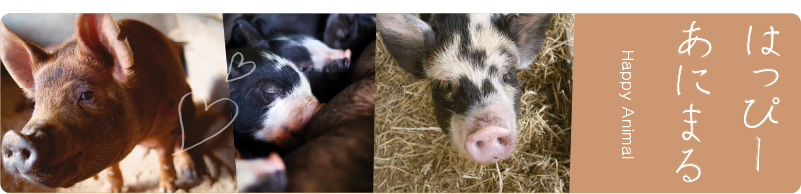「ボクはポニーなので……」
ウマは身近な動物といえるでしょうか? 「ウマを毎日見る機会はないけれど、身近な動物な気がする」という感じではないでしょうか。テレビをつけていると、ウシやブタよりは多く取り上げられている気がします。私たちがウマをなんとなく身近に感じるのは、人類がはるか昔から、ウマをいろいろな形で利用しているからかもしれません。
ウマの利用といえば、まず乗馬が思い浮かびます。乗馬にも、競馬や障害などの競技、乗馬クラブやトレッキング、海外では警察官がサッカー場などの警備で使用することもあります。ペットとして飼育されている場合もありますし、観光用として利用しているところも多くあります。最近は、アニマルセラピーという治療行為への利用も注目されています。また、一部では食用として利用している地域もあります。私が生活している熊本は馬肉の産地ですし、意外なことにフランスは馬肉を食べる文化があります。このようにウマは、最も多様に利用されている家畜といえるでしょう。
そして、動物としてのウマは、“早く走る”ということを特徴としています。草食動物というと、肉食獣に食べられる立場ということもあり、弱い動物というイメージが先行してしまいがちです。しかし、草をエネルギーにして、あの体を維持するのは、非常に優秀な仕組みがあるからこそなのです。(ヒトでは、ベジタリアンと呼ばれる食生活の方もいらっしゃいますが、草食動物のように植物体の実を食べず、調理しない生の草だけでは生きていくことは困難です)。
大型草食動物であるウシとウマの大きな違いは胃の数です。ウシは、胃を4つ持ち、最も大きいな胃(第一胃といいます)に、各種の微生物を飼育しています。取り込んだ草を微生物に分解してもらうのです。この方法は食いだめをすることができるので、摂食行動(草を食べる行動)に費やす時間を短くすることが可能ですが、体が重くなるという欠点があります。

一方のウマは、ウシやヒツジのような「4つの胃」を持っていません。腸内発酵という方式で粗繊維成分を分解吸収します。この方式は、ウシのように食いだめができませんが、体が軽くなるという利点があります。放牧されているウマを観察していると、頭を下げて草を食べる行動が多いという印象を受けますが、ウマは1日の長い時間、摂食行動をしないと体を維持できないからなのです。つまり、ウマは逃げるためのスピードを選択してきた動物といえます。
このように、食べ物を消化する仕組みや、進化の歴史を理解すると、ウマという動物の特徴がより明確になり、ますます身近に感じることができるのではないでしょうか。