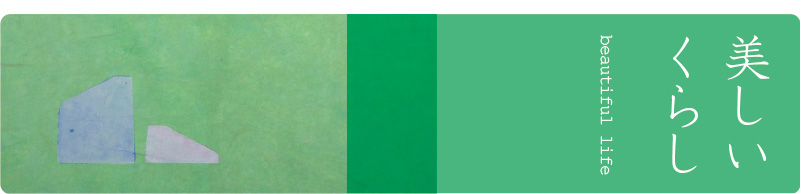真っ赤なクランベリー
どの季節に訪れても、バルト三国の食卓に欠かせない食材があります。それは、ベリー。
夏になると、マーケットは一気に色づきます。イチゴやラズベリーを筆頭に、さまざまなベリーが宝石のように並び、通りすがりの人々の足を止めさせるのです。5月ごろから姿を見せ始めるイチゴに始まり、季節が進むにつれてラインナップはますます充実します。買い物かごがキロ単位のベリーでいっぱいになる光景は、こちらの人々にとって当たり前。日本のように小さなパックをそっと手に取る感覚とはまるで違います。
庭を持つ人々は自分でベリーを育てていますし、森へ足を運べば、ビルベリーやハスカップ、クラウドベリーといった野生のベリーを収穫することもできるのです。多少の労力を要しますが、どれも新鮮で無農薬。まさに「森の恵み」を手に入れることができます。
秋や冬になっても、ベリーは食卓から消えません。夏に摘んだ実がジャムやジュースに姿を変えて登場するのです。
とある家庭の地下室にお邪魔したときのこと。ずらりと並ぶ瓶詰め――キュウリやトマトのピクルス、キノコのマリネ、ベリーやリンゴのジャム。その光景に思わず「ここは食品倉庫か何かですか?」と声が出てしまったほど。中には業務用の冷凍庫を設置し、加工せずそのまま保存している猛者もいます。輸入食品が簡単に手に入る今でも、こうした保存食文化が根強く残っているのは、かつてのソ連時代、冬に手に入る食料が限られていた記憶が影を落としているのかもしれません。そして何より、自分で作る安心感――これもまた大きな理由なのです。
10月初旬、私はエストニアのタルトゥ(Tartu)の森を訪れました。案内してくれたのは、私のパートナーの大学時代の友人、マーリヤ(Maarja)さん。いつも元気で朗らか、4人の子どもを育てるたくましいお母さんです。彼女はエストニア最大の湖・ペイプシ湖を源とするエマ川(Emajõgi)の湿地公園のプロジェクトマネージャーをしており、この付近の森や自然にとても詳しいのです。
東京ではまだ軽やかな秋風が吹くころですが、エストニアはすでに冬の始まり。マフラーに毛糸の帽子、手袋、中綿ジャケットの上にウィンドブレーカーを羽織ります。
「先週までは本当に暖かかったの。でも、今年は9月末までキノコが採れたのよ。いつもの年じゃ考えられないわ」マーリヤさんがそうつぶやきました。気候変動の影響は、エストニアの森にも現れています。
「実はね、クランベリーの場所を見つけたの。今日は一緒に摘みに行きましょ!」
そのひとことに、胸が高鳴りました。なんと彼女は、私が訪れる前に下見までしてくれていたのです。日本からやって来て、もし「ベリーがなかったら……」と心配してくれていたのです。
「マーリヤさん、優しすぎますよ……今日は絶対、たくさん摘みます!」
タルトゥ中心部から車で15分ほど。エンジンを切った先は、舗装されていない林道。長靴に履き替え、かごを手に森へと入っていきます。
一歩森に足を踏み入れると、辺りはコケの緑に包まれ、黄色や茶色のキノコ、落ち葉が織りなすじゅうたんのような地面。季節が夏から冬へと移り変わるその途中の森の空気が、肌を通して伝わってきます。いくつもの分岐を、マーリヤさんは記憶だけを頼りに進みます。「よし、合ってる。この池があるから間違いない!」彼女が指差したその先には、「池」と呼ぶには大きすぎるほどの水面が広がっていました。そして、その奥に――
「見て!クランベリーのじゅうたんよ! 誰にもまだ採られてないわ!」
そこには、私たちだけの秘密の森。コケの間から顔をのぞかせる紅色の実たちに、思わず「わーお!」と声が出ました。
「日が暮れる前に、できるだけたくさん採ろう!」摘み採りモードになった私たちの目のセンサーは、完全にクランベリーをターゲットに反応中。硬くてぷっくりとした直径1cmほどの実を、ひとつひとつ、かごに落としていきます。フレッシュなクランベリーは、日本でよく見かける甘いドライフルーツとは別物。口に入れた瞬間、目が覚めるような酸っぱさが広がります。「これは……ジャムにしないと無理!」とすぐに理解しました。

クランベリーの入ったかごを手にするマーリヤさん
ずっと前かがみでクランベリーを摘み続けるうちに、腰は悲鳴を上げます。時折立ち上がっては、森の静けさに包まれながら大きく背伸び。そして気づけば、お互いの姿が見えなくなっていました。「マーリヤーー!」 「ケイコーー!」声を頼りにお互いの位置を確認し合いながら、また黙々と作業を再開します。気づけば1時間半が過ぎていました。
「帰る?」 「……もうちょっとだけ!」
名残惜しさに勝てず、私のわがままにマーリヤさんは笑って「じゃあ、あと30分だけよ!」。その最後の30分、心の中でタイマーを刻みながら、私はただひたすらクランベリーを追い続けました。けれども30分はあっという間に過ぎていき……。
「あぁ、ここにテント張って、ひと晩中摘みたい!」
そう森に向かってつぶやきながら、私は名残を惜しみつつ、クランベリーのじゅうたんからそっと足を離したのでした。(つづく)
★「エストニア料理屋さん」のホームページは
コチラ⇒★バルト三国の情報サイト「バルトの森」は
コチラ⇒ ◎佐々木さんのインタビュー記事「キッチンで見つけた素顔のエストニア」は
コチラ⇒