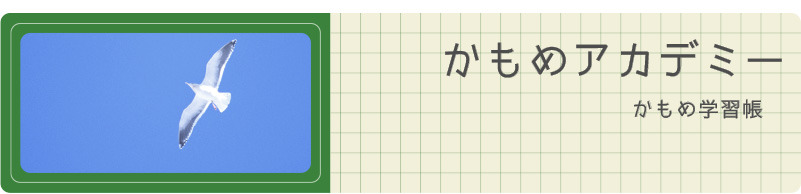戦争は常に虚しく、ひとたび始まってしまえば個人で
抗うことは不可能です。敵と味方に分かれ、それぞれの命を奪い合うのが戦争の実態。そこでは人間の明暗すべてが、否応なしに
顕れてしまいます。
世阿弥が確立した能のジャンル・軍体能「修羅物」について、彼自身は作劇ガイドと言うべき著作『三道』に「平家の物語のままに書くべし」と説いています。けれども、日本史上最大の国民文学『平家物語』から誰をどう抽出し、どう描くか。その可能性は無限に広がります。
戦争におけるさまざまな場面では、「殺し、殺される者同士のドラマ」が生まれます。それを最も「物語のまま」冷徹に描いた能が〈
敦盛〉ではないかと、私は思います。
平敦盛(1169~84年)は清盛の弟・
経盛の末子。俗に「
無官太夫」と呼ばれました。

月岡耕漁『能楽図絵』より能〈敦盛〉
若武者として麗しい姿を見せる後シテ。一ノ谷の合戦で戦死して修羅道に堕ち、生前の敵将・
熊谷直実を前に心荒ぶる場面である。画面の右に群れ飛ぶのは須磨の浦に名高い千鳥。合戦
前夜、平家の陣所で歌舞に興じたさまを回想する能の後場《クセ》で、「千鳥の声もわが袖も、
波に萎るる磯枕」とある。
敦盛戦死の旧跡、摂津国(現在の兵庫県東部)須磨の浦を訪れた蓮生法師の前に笛を吹く草刈りたちが現れる。在所にも似ぬ風雅な若者(前シテ)は「敦盛ゆかりの者」と名のり、蓮生に十念(念仏を十遍唱える法儀)を授けてくれるよう願って、消え失せる。
夜もすがら敦盛の死後を弔う蓮生の前に、生前のきらびやかな軍装で敦盛の霊(後シテ)が出現する。平家流浪のさまを回想した敦盛は一ノ谷合戦前夜の遊舞を回想しつつ([中ノ舞])、敵将・直実いまは蓮生法師に挑み掛かろうとするが、「仇をば恩」と思い直し、死後は蓮生と同じ蓮の上での極楽往生を願う。
修羅物に限らず、能は多くの場合シテ一人のドラマに焦点が結ばれます。この〈敦盛〉もそうではあるものの、ワキの存在感は別格です。今や出家し「蓮生法師」と名のる人物は、もとの俗名・熊谷次郎直実(1141~1207年)、つまり「シテ・平敦盛を殺した本人」なのです。
「殺し、殺される者同士」をワキとシテに
対峙させた修羅物は、ほかに一つもありません。ここには、戦争の本質的な構造が隠されています。世阿弥の自信作でもあるこの能には、このような突出した特色があるのです。
前シテは同行のツレを伴った、身分の
賤しい草刈り男です。漢詩文には「
樵歌/
牧笛」という成語があります。麗わしい詩文にしばしば詠まれる「木こりの歌声/牧童が吹く笛の音」は、教養の高い皇族・貴族・高僧や高級武士(すなわち能役者のパトロンたち)が親しむ文学世界で公認された風雅の定型でした。能の登場人物を「笛吹く草刈り」と設定した趣向(これは『平家物語』と無縁な世阿弥の創意)には、高度な文雅を喜ぶ「
上方(高位のVIP)」に
秋波を送る世阿弥の芸能戦略が潜んでいます。
地謡/身のわざの、好ける心に寄り竹の、好ける心に寄り竹の、小枝、蝉折、さまざまに、
笛の名は多けれども、草刈りの吹く笛ならば、これも名は「青葉の笛」と思しめせ。住吉の
汀ならば高麗笛にやあるべき。これは須磨の塩木の、海人の焼きさしと思しめせ、海人の焼
きさしと思しめせ。 「高麗笛」が今も使用される雅楽器であるとおり、この短い一段は楽器尽くしになっています。敦盛が愛用した横笛「青葉の笛」は戦前の小学唱歌で誰もが知っていた名。「小枝」はその異名とも伝え、「蝉折」もまた平安時代末期によく知られていた笛の名器でした。敦盛が心を寄せた音楽、ことに横笛の風雅は、戦闘を事とする修羅物の能の殺伐とはかけ離れた美の世界にわれわれを
誘います。
戦場を描きながら、美の世界に触れる。これこそが、世阿弥の創作した修羅物の極致なのです。
このあと、一人残った前シテ・草刈り男は、蓮生に十念授与を望みます。「殺し、殺された者同士」の、生死を超えた信仰の紐帯。後場に至ってこれを回想すると、この場は実に深いものとして胸に迫ります。
なお、この能の前シテは
直面(素顔)で勤めます。後シテが露もしたたる美少年役だけに、前場で素顔を曝しその化身を演ずることに照れて拒む能役者が多く、〈敦盛〉は最高の名曲でありながら滅多に舞台に掛かりません。その点でも実に皮肉な難曲なのです。
シテは楽屋で扮装を改め、敦盛の霊となって再登場します。後シテは面を使用しますが、一説に敦盛の没年と伝えられた「十六」という名の品位ある美少年の相貌。古来、いかにこの能が愛されていたかが分かります。
寿永3年/治承8年2月7日(当時の西欧ユリウス暦では1184年3月20日)の一ノ谷合戦。その前夜、平家の陣所から夜もすがら音楽の響きが聴こえたと伝えます。源氏に追われ、都を捨てて逃亡して1年。敦盛は、わが身の成り行く先を悟り、回想にふけります。
地謡/しかるに平家、世を取つて二十余年。まことに一昔の過ぐるは夢の中なれや。寿永の
秋の葉の四方の嵐に誘はれ、散り散りになる一葉の、船に浮き波に臥して夢にだにも帰ら
ず。籠鳥の雲を恋ひ、帰雁列を乱るなる。空、定めなき旅衣。日も重なりて年月の、立ち
帰る春の頃この一ノ谷に籠もりて、しばしはここに須磨の浦。
シテ/後ろの山風、吹き落ちて、
地謡/野も冴え返る海際に、船の夜となく昼となき、千鳥の声もわが袖も、波に萎るる磯
枕。海人の苫屋に共寝して須磨人にのみ磯馴松の、立つるや夕煙、柴といふもの折り敷
きて、思ひを須磨の山里の、かかる所に住居して、須磨人になり果つる一門の果てぞ悲し
き。 《クセ》と呼ばれる舞いどころです。一ノ谷にほど近く、敦盛が戦死した須磨は『源氏物語』で光源氏がわび住まいの日々を送った、風雅のイメージに満ちた名所でした。後の人々もその符合に深い意味を感じ、須磨の浦で落命した若武者・敦盛の最期を心から悼んだのです。
これに続いて敦盛は[
中ノ舞](流儀によっては[男舞]「
黄鐘早舞」)を舞います。囃子事(笛・小鼓・大鼓)のみの舞は麗しい女のシテが舞うのが本義ですから、修羅物では異数の例外。この能の敦盛は「美女に見まがう美少年」として造形されていることがよく分かります。
舞い上げた敦盛は、安徳天皇の
御座船(
御船)をはじめ落ち延びた平家一門に、思わず取り残された失態を悟ります。いよいよ能の最後です。
シテ/さるほどに、御船を初めて、
地謡/一門皆々、船に浮かめば、乗り遅れじと汀にうち寄れば、御座船も兵船も、遥かに延
び給ふ。
シテ/せんかた波に駒を控へ、呆れ果てたるありさまなり。かかりけるところに、
地謡/後ろより、熊谷の次郎直実、逃さじと追つ懸けたり。敦盛も、馬引き返し、波の打物
抜いて、二打ち、三打ちは打つとぞ見えしが、馬の上にて引つ組んで、波打際に落ち重なつ
て、つひに討たれて失せし身の、因果は廻り合ひたり。敵はこれぞと討たんとするに、仇を
ば恩にて、法事の念仏して弔はるれば、つひには共に生まるべき同じ蓮の蓮生法師。敵にて
はなかりけり。跡弔ひてたび給へ。跡弔ひてたび給へ。 ワキ・蓮生は舞台の右手前に静かに坐したまま動じません。敦盛の霊が心を怒らせ、太刀を抜き「敵はこれぞ」と迫っても、眉一つ動かさないのです。その鉄壁不動の信仰心が敦盛の亡魂を救い、「つひには共に生まるべき同じ蓮」と怨念も消えた清浄な悟りに導く感動。
『平家物語』には熊谷が心ならずも敦盛を手に懸け、この心の傷が原因で出家し、ついに法然上人の
仏弟子となった次第が説かれます。真相は複雑ですが、直実あらため蓮生が法然の門弟だったことは事実。その出家の
発心に、わが子ほどの若武者を斬らざるを得なかった深い悔恨があるとしたら……この連載で何度か述べた通り、武士とは「殺人のプロ」でした。その本務から脱してまで、深い仏教的寛容にともに抱かれた熊谷と敦盛。
この1年にわたる連載「能で読み解く源平の12人」。結局は都合13人になりましたが、最後にあたり敦盛と熊谷、敵味方の2人を採り上げたのは、世阿弥の能〈敦盛〉に描かれた「殺し、殺される者のドラマ」が、最後は「仏教的寛容で救済に至る」絶大な感動によるためです。
能とは実に深く、熱い、現代においても古びない心のドラマです。
この醍醐味を、みなさんもぜひ実際の舞台に接し、とくと味わって頂きたいと念じています。(おわり)