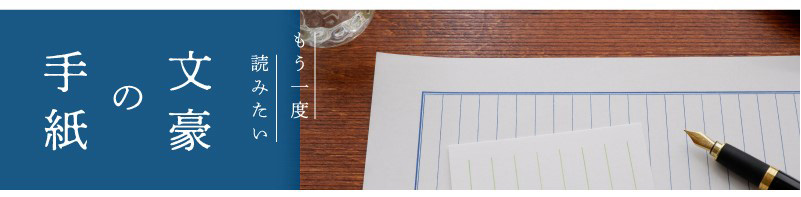手紙がとりもつ人との結びつきには、文のとり交わしを重ねた相手だからこそ伝わる心情や、相手を思う気持ちから生まれた心の変化によって、関係をより深化させていく力があります。この連載では、経営者・ビジネスパーソンへの手紙の書き方の助言や、企業内外向けの文書制作を手がける近藤さんが選んだ「もう一度読みたい文豪の手紙」を読みながら、人の気持ちを知り、自己を変えていくための手紙と書き方のポイントを学んでいきます。 文学者・川端康成と、戦後の荒廃した人々の心を潤したと賞される日本画家・東山魁夷。戦後日本の文学界と美術界を代表する二人にはお互いへの書簡が多く残されています。両者の手紙は、儀礼的な挨拶やお礼を目的とするものにとどまりません。礼節の中にも親しさが広がるやりとりに、大人の素敵な在り方を教わる思いがします。共に美しさを究めた二人が、手紙を介してどのような交流をつむいでいったのかをご紹介してまいります。
交流のはじまり
二人の出会いは、1955(昭和30)年4月、川端の小説『虹いくたび』(河出書房)の装幀を東山が担当したことからはじまります。
これを機に、東山は鎌倉にある川端邸を訪問する機会を得ました。川端56歳、東山47歳の時でした。面会後に東山は川端に礼状を送り、その後川端からも東山の個展を鑑賞した感想などが手紙で寄せられ、こうしてはじまったやりとりは以降17年間続きます。
洋の東西を問わず骨董・美術品を蒐集する共通点もあった両者は公私共に親しくなっていき、川端は東山が画集を出版するたびに序文を手がけました。
ノーベル文学賞受賞の夜に
1968(昭和43)年10月17日、川端は日本人初のノーベル文学賞を受賞しました。
その夜、東山は妻を伴い、川端の自宅にお祝いに駆けつけます。たくさんの報道陣が押し寄せている中、川端は奥の書斎に一人でひっそりと座り、東山夫妻を迎えました。
東山はお祝いを述べた後、川端の多忙の極みを思い、今回の序文を遠慮する旨を伝えました。ちょうどこの頃、東山は『京洛四季』という画集を刊行する予定であり、序文を川端が手がけることになっていたからです。
すると川端は平然と「いや、忙しくなんかありませんよ。近いうちに京都へ行って書いてきます」と返したとのちに東山は振り返ります。
この画集『京洛四季』は、川端が東山に「京都のあるうちに描いておいて下さい」と何度も話していたことをきっかけに生まれた作品群でした。そのため川端にとっても思い入れがあることは想像に難くありません。しかしながら、自身が日本人初のノーベル文学賞を受賞したという晩ですらも普段通りを装い、相手を気遣うというのはやはり並大抵ではできることではなく、川端の東山に対する敬意の深さが感じられる、二人の親しさが伝わる出来事だと感じます。
その一週間後に送られた東山によるこの日のお礼の手紙には、
「拝啓 先日は夜おそくお伺ひ致しましてお邪魔致しました。
先生の御受賞が国を挙げての大きな喜びになり、誠に嬉しいことに存じます。
先生から日頃親しくして戴いてゐます私共は、言葉に云ひ尽せない感動を日増しに深く感じて居ります。
先生の御作品や御人柄は今回の御受賞の有無にかゝはらず、この上なく尊敬申上げて居りますのですが御厚情に甘えて失礼ばかりして居りましたことが、今更のやうに恥かしく申訳けなく存じます。
先生の御作品を通じて日本人の美の心が、世界の人の心に触れ合へるといふことが一番嬉しく感じられます。
先生はいつも私の美を求める心の大きな支へとなり励みになつてゐて下さるのです。(後略)」
(10月25日付け 『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』84頁)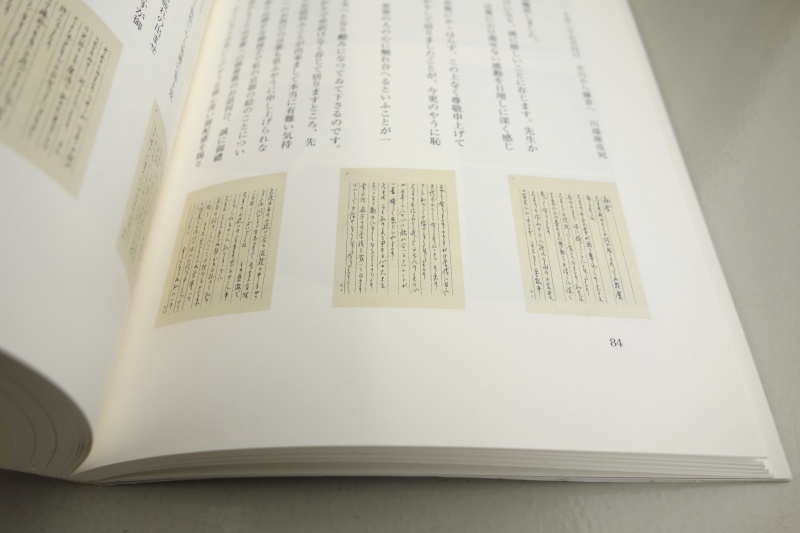
川端のノーベル文学賞受賞一週間後に送られた東山の手紙(『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』より)
とあり、限りない感謝と敬愛の気持ちを表しています。
これまでの手紙には無いほど「先生」としきりに呼びかけている点や、全ての「先生」の文字を必ず行の先頭にしていることなどから、敬意を最大限に表現していることが一見して伝わります。
海外からの手紙
同年の1968(昭和43)年12月10日、川端はスウェーデンのストックホルムにて行われたノーベル文学賞の授賞式に出席しました。
授賞式を終えたのちヨーロッパへ休養旅行に赴き、途中ロンドンから東山に手紙を出しています。普段は和紙に毛筆であることが多い川端も、この時は滞在したホテルの便箋を使用していることや、日頃の見事な運筆もこの手紙ではどことなく朗らかで読みやすくやわらかい筆跡であり、それまでとは全く違うものになっています。
また、手紙には「なほ、帰国は来春の予定ですので年末年始の御あいさつもここに申上げさせていただきます。」
(12月20日付け 『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』88頁)とあり、この暮れの手紙によって、旅先からの手紙は終わるように思われます。しかし、直後の69年1月上旬にはイタリア・ソレントから東山の自宅に絵葉書が届きます。年始の挨拶を年内の手紙でまとめてしたはずの川端は、きちんと旅先から年賀状も出しているのです。
「謹賀新年 (中略)シエナの町と美術、印象的でした。帰つて御作をわが家の床の間で見るのが何よりの楽しみです。
寝正月ナポリの海のしぐれにて
元旦やベスビオの上に去年の雲」
(1月初頭 『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』90頁) こんなに素敵な年賀状はなかなか見当たりません。
また、東山も妻を伴い、同年の4月30日から4ヵ月ほどドイツ・オーストリアの旅に出ました。ドイツ・ベルヒテスガーデンからホテルの便箋を用いて川端宛に手紙を出しています。普段は便箋何枚にも渡りしたためる東山ですが、この時は1枚にぎっしりと文字を書き入れ収めています。やはり旅先の手紙というものはすこし気持ちが明るく、軽快な雰囲気を纏うようです。
突然の別れ
その後も仕事上のみならず、家族ぐるみで付き合い、旅行を共にするほど親しくしていた川端と東山。1971(昭和46)年、川端は集英社の『東山魁夷代表画集』の序文「東山魁夷私感」を書くため、東京国立近代美術館へ訪れ東山の作品を鑑賞するなどし、その年の東山は日本各地で個展を開催しており、その間にも二人の手紙のやりとりは続いていました。
しかしながら、翌72年4月16日に川端は突然、自裁します。享年72歳でした。
川端の死から約2ヵ月後の6月に『新潮』臨時増刊号「川端康成読本」が刊行されました。
東山はこの表紙画・装幀を務め、追悼文「星離(わか)れ行き」を寄稿し悲しみを表しています。その内容は、各地で個展開催をしているその合間に川端宛に葉書を書いていたという回想からはじまります。
ご無沙汰しているお詫びをしたためていたその時、空には上弦の月が懸かっていましたが、真上に輝く大きな星が、尋常でないものを感じさせたと東山は振り返ります。そのあまりの閃きに妻を呼び、しばらく星を見つめ窓辺に立ちつくしたその時刻が、川端の旅立ちの時だったようだと記しています。
東山が見た星の光
東山は追悼文に川端との出会いを「心の支え、励まし、喜びであり、畏れであった。」と記し、「先生は私を敬虔な者として遇していて下さった。」と述べました。そして「あのように、私に親しんで下さったのは、(中略)先生も私も、お互いに、孤独な心と心の巡り合いを、大切にしたい気持ちが強かったからでもあろう。」と残しています。
川端は幼い頃に父母を病で亡くしており、4歳違いの姉は親戚に預けられましたが、早くして亡くなっています。祖父以外の肉親の顔を覚えていないと随筆に残していますが、その祖父も川端が15歳の頃に旅立ちます。さらには祖父の死と同時に家屋も失うことにもなりました。
東山もまた、最後の肉親だった弟が亡くなった頃、住む家も定まっていなかったという時代がありました。空襲により元の住まいをなくし、知人宅の2階の一部屋を間借りし絵画の制作をしていたのです。東山38歳の頃でした。
肉親の喪失を何度も体験するのと同時に様々なものを失った川端と東山は、お互いにどこか近しいものを感じていたのかもしれません。
愛する身近な人々が旅立つ時、東山は光を感じていました。「天草灘の夕べの空と海の色、西方に輝いた星の光を、生涯忘れることがないであろう。時が経つにつれて、それが先生の魂から発した光芒ではなかったかと、ますます強く思うようになりそうである。」と東山は川端との最後の思い出を結んでいます。
「私の貧しい画集にこの上ない光輝をお与へ下さいましたことを深く感謝申し上げます。」
(1959年11月12日付け 『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』25頁)とかつて手紙で述べた東山にとって、川端は間違いなく眩い光であったことでしょう。
そしてまた川端にとっても、東山の描く深い寂寥を越えた静謐な絵画と東山の人柄に、どれほど心を慰められたことでしょうか。
よろこびを共にできる幸せ
以上、川端康成と東山魁夷の交わした手紙の一部をご一緒に拝見してまいりました。
ここで改めて、敬虔な手紙とはなにかを考えてみたいと思います。
川端は東山との出会いについて「私はもう六十歳に近かつたが、その年でなほ新な親接の知己を得る幸ひも、人生にはあつた。」
(※東山への手紙の一節――「星離れ行き」)と当時を振り返っていました。
思いがけず親しい友人ができる幸いは、どなたにとってもかけがえのない喜びであると思います。しかしながら、その気持ちをずっと持ち続けることができたのは、お互いが尊敬しあうだけではなく、敬愛の念を抱いていたからと考えます。
また、川端はノーベル賞受賞記念講演に際し「美しい日本の私」を記したその中で、日本美術の特質のひとつは「雪月花の時、最も友を思う」という詩語に集約されるという話をしました。
文学という形で日本の美を紡いだ川端は、例えば雪や月、花の美しさを見るにつけ、東山の作品を思い、その心で手紙をしたためたのではないでしょうか。
四季折々、または作品を鑑賞し手にした時。美しいと思うそのよろこびを共にできる幸せを感じて手紙を書く。その美に巡りあえた幸福の気持ちが、敬虔な手紙を成り立たせていると思われます。
ある日の手紙に、東山はもみじを同封しました。
手紙は「拝啓 秋も深くなつてまゐりました。」とはじまり、北海道と東北の秋を見に旅をしていたことが綴られ、追伸の形で末文に「北海道のもみじ御覧に入れます。」とあります
(1966年10月22日付け 『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』58頁)。なんとそのもみじは手紙と共に現存しており、川端夫妻が大切に保管していたことが伺えます。この手紙は川端の講演の2年ほど前ですが、「雪月花の時、最も友を思う」を東山は体現していたのです。
美しいものに出会った時、ふと思い浮かぶ人はいますか? そのような時に、手紙でお裾分けできたらとても素敵です。例えばそれが物質ではなく、一言、手紙の端に書き添えるだけでもよいと思います。美しさに触れた時、美に巡りあえた幸いをあなたと共にしたい、という気持ちは、この上なく美しく、敬虔なものであると言えるのではないでしょうか。
(つづく)

©2022 POSTORY
近藤さんより
「巻紙・五雲箋を用いて、川端と東山の交流のきっかけとなった『虹いくたび』をイメージした手紙を撮影しました」
<参照文献>
東山魁夷『泉に聴く』(1972年 毎日新聞社)
川端香男里・東山すみ監修『川端康成と東山魁夷 響きあう美の世界』(2006年 求龍堂)
平山三男他『巨匠の眼 川端康成と東山魁夷』(2014年 求龍堂)
佐々木徹『東山魁夷ものがたり』(2002年 ビジョン企画出版社)
『川端康成全集』(1980-1982年 新潮社)【POSTORY】
https://postory.jp/