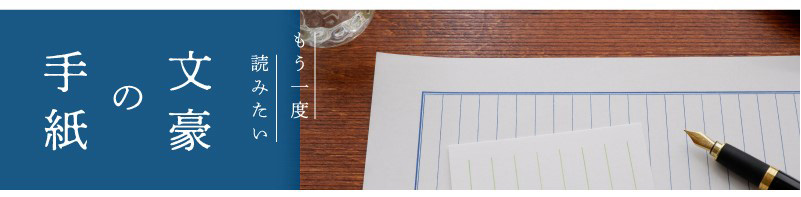1923(大正12)年に文藝春秋社を創業して出版事業を手がけた菊池寛は、大正・昭和前期に人気大衆小説作家としても活躍しました。実業家兼作家として多忙な日々を送る中で、趣味に仕事に羽ばたいた彼は、一方で《速達の菊池》とあだ名がつくほど、友人知人に宛てて頻繁に速達の手紙を送りました。気持ちが昂ぶることが多くあり、早急に伝えるための速達だったといいます。今回は菊池寛が残した手紙にふれて、活躍の裏に秘められた葛藤と、手紙を介した感情の析出をご一緒に見てまいりましょう。
学校よりも図書館に通った青春時代
菊池寛は1888(明治21)年に香川県高松で生まれました。菊池家は代々儒学者の家柄でしたが明治時代には没落しており、家は貧しかったといいます。七人兄弟の四男であった菊池は子どもの頃から本が大好きで、13歳の頃には雑誌『文芸倶楽部』の購読をはじめ、尾崎紅葉や幸田露伴、泉鏡花の作品に親しみました。16歳の時に高松に図書館が開館した際には真っ先に訪れました。約2万冊あった蔵書のうち少しでも気になる書籍にはすべて目を通したといいます。のちに菊池は速筆で有名になりましたが、読むこと、そして記憶力も大変に優れていました。
そんな若き日の数々の本との出会いの中でも、ひと際、菊池を感激させた機会がありました。それは21歳の時に通っていた早稲田大学でのことでした。
早稲田大学への在籍は3ヵ月と短かったこともあり、あまり思い出がないとする菊池ですが、忘れられないことが一つだけあったといいます。それは、大学図書館で井原西鶴の全集を読んだことでした。1928(昭和3)年から翌年にかけて『文藝春秋』に連載した「半自叙伝」で次のように振り返っています。
「さすがに、文科を尊重する早稲田なるかなと、感嘆したほどだった。(中略)星移り物変り、古今東西の文芸書にも、ちっとも感激しなくなった今も、西鶴だけはやはり愛読書の一つとして、数え得るほど西鶴は好きである。従って、早稲田で初めて西鶴を読んだ記憶は僕として忘れがたい感激である。」
ありとあらゆる分野の書物を読破してもなお、読めた喜びに涙を流すほど読みたい本があったという菊池は、読書の楽しさ、そのエンターテイメント性を人一倍理解していたのでしょう。だからこそ、『真珠夫人』に代表されるいわゆる「通俗小説・大衆小説」というジャンルを手がけ、多くの人々に「読む」娯楽を提供したのかもしれません。
この「半自叙伝」では、執筆当時40歳になっていた菊池が、自身の過去を振り返る興味深い言葉にふれることができます。「私は半生を学校へ通うよりはもっと熱心に図書館へ通った男である」と述べる一方で、「自分は個人主義、自由主義、人道主義を標榜していた作家」とも記しています。若き頃の熱心な図書館通いは、まさにそれらの主義を培っていたように感じます。ただし、現在「個人主義」と聞いても穏健ですが、当時は危険思想のように扱われる主張でした。19歳の頃、東京高等師範学校に進学するも、翌年除籍されてしまった理由の一つには、この「個人主義」をクラス会などで唱えていたことがあると言われています。
『新思潮』の仲間たち

第一高校在学時の菊池寛
(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)
読書好きな青年の将来を決定づけたのは、1910(明治43)年、21歳の時。3ヵ月通った早稲田大学を離れて入学した第一高等学校で出会った、文学を志す同級生との交友でした。同級生には、菊池とともに『新思潮』のメンバーになる芥川龍之介、久米正雄、松岡譲、成瀬正一がいました。
『新思潮』は1907年に劇作家・小山内薫により創刊され、のちに継続的に発行されていった文芸同人誌です。第2次からは東京帝国大学の学生らによって発行される同人誌になりました。
菊池は第一高等学校から京都帝国大学へ行き、芥川、久米、松岡、成瀬はともに東京帝国大学へ進学しました。そして、彼らは『新思潮』を発表の場に、文学活動を歩みはじめました。

1916(大正5)年頃の第4次『新思潮』のメンバー。左から久米正雄、松岡譲、芥川龍之介、成瀬正一
(出典:『芥川龍之介作品集第1巻』)
1916(大正5)年2月から翌年3月にかけて出された第4次『新思潮』は、この同人誌の歴史の中でも語り草になっている「伝説の雑誌」です。菊池、芥川、久米、松岡、成瀬という第一高校時代の同級生5人をメンバーに刊行され、創刊号に芥川が発表した「鼻」が夏目漱石から絶賛されたのです。5人は漱石と面会する機会を得て、芥川、久米、松岡、成瀬は私淑していきます。
菊池はというと、芥川らと漱石の木曜会に出席するも、友人らが傾倒するほどには漱石本人に親しみませんでした。漱石が周囲に、菊池の作品と風体について軽妙に語ったためと言われています。漱石自身は悪意のない言葉だったとしても、作品のみならず見た目に触れられたことに菊池は気分を害したのでしょう。たとえどんなに豪傑な人物でも、煩悶する心を持たない人などいません。容姿は菊池のコンプレックスの対象でした。
ちなみに、1921年から23年にかけて出された第6次『新思潮』には川端康成が参加しています。この当時、菊池は新聞連載で自身として初の大衆小説『真珠夫人』に取り組んでいる最中でしたが、結婚準備のために仕事を欲していた学生の川端に住む家を無料で貸し与え、当面の生活費を毎月支払う約束をし、実行しました。
親分肌であった菊池には、なんとも気前のよい逸話が多数残されています。
文学を愛したリアリスト
1916(大正5)年に京都帝国大学を卒業した菊池は、時事新報社に入社し社会部記者になりました。
翌年には代表作の一つとなる戯曲「父帰る」を第4次『新思潮』に発表します。続いて、京都に移り住んだ学生時代を下敷きにした作品「無名作家の日記」などが認められ、文壇での地位を確立していきました。
さらなる転機は、1920年に大阪毎日新聞と東京日日新聞に連載した大衆小説『真珠夫人』でした。この連載の成功により一躍スターダムに上りつめます。
『真珠夫人』に取り組んだ当時を、「半自叙伝」の続稿で次のように振り返っています。
「私は文壇に出て数年ならざるに早くも通俗小説を書き始めた。私は、元から純文学で終始しようと云う気など全然なかった。私は、小説を書くことは生活のためであった。青少年時代を貧苦の中に育ち、三男ではあるが没落せんとする家をどうにかしなければならぬ責任があった。(中略)清貧に甘んじて立派な創作を書こうという気は、どの時代にも、少しもなかった。」
このように書く菊池ですが、決して純文学の芸術性を否定しているわけではありません。菊池には、芸術とは一般に開かれるものであって一部の人々の占有物ではない、という強い思いがありました。そして、その思いをビジネスとして実践しようとしたのが、文藝春秋社の創業でした。
『文藝春秋』の誕生
1923(大正12)年1月、小石川区(現・文京区)の自宅に文藝春秋社を設けた菊池は、月刊誌『文藝春秋』を創刊します。35歳の時でした。
創刊号は、本文28ページの薄い小冊子でしたが、菊池にとっては気兼ねなしに自由に書き編集できる媒体でした。創刊時の『文藝春秋』は、今より小ぶりなB6判で価格は10銭。創刊号の執筆者には芥川や久米ら友人たちが名を連ねました。発売から3日で創刊号の3000部は完売したそうです。翌月の第2号には横光利一、川端康成らが加わりました。
第4号では1万部に達するなど順調な出だしでしたが、その年の9月1日に状況を一変する事態が発生します。東京や神奈川を襲ったマグニチュード7.9の大地震、関東大震災です。死者行方不明者14万人以上にもなった大災害は、菊池の心境にも変化をもたらしました。それは、生死の問われる状況においては、文芸芸術が無力である、という考えです。
震災の発生から5日後に、詩人の薄田泣菫に宛てて書かれた手紙が残されています。
「啓 小生は幸にして何の被害もありませんでしたが、もう文藝藝術は、二三年は駄目です。(中略)武者小路にならって、百姓をやらうと思ってゐます。とにかく、生活と云ふものゝ真諦が分かったやうな気がします。享楽生活、文化生活と云ったやうなものが、いかに、頼みないものかと云ふことが分かりました。自分で働いて、淡々たる簡易生活をやるのが一番いゝと云ふ気がします。とにかく、今の東京はたゞ喰ふことと寝ることが尤も大切なことです。(後略)」
(薄田淳介(泣菫)宛ての手紙 9月6日付け) 震災という未曽有の出来事に打ちひしがれるも、菊池は東京での生活を続け、雑誌編集の仕事も執筆活動も継続していきました。とことんリアリストであり、文芸芸術は生活の二の次であると唱えた菊池寛。たくさんの人々に、生活の中で楽しんでもらえる仕事を善とすることで、『文藝春秋』のビジネスはより加速していきます。
震災から明けた1924年の新年号は1万7000部、翌25年新年号は2万6000部となりました。その翌年の1926(大正15)年は大正最後の年です。新年号は一挙に11万部へと躍進の道をたどりました。
昭和の幕が明け、文藝春秋社がいよいよ時代に勇躍する出版社として名乗りを上げていく中、1928(昭和3)年には会社を株式会社化して、菊池は代表取締役社長に就任しました。
1935年には自社の文学賞として芥川龍之介賞・直木三十五賞を設けます。1927年と1934年に没した芥川と直木は、菊池が若き日に出会った親友であり、二人は『文藝春秋』の草創期を盛り上げたスタープレイヤーでした。
両賞が現在も続いていることは、皆さまのご承知の通りです。芥川賞は純文学系の新進作家の登竜門として、直木賞は大衆文学系の作家に与えられる賞として、俊英を世に知らしめる顕彰が行われています。
姿を見ぬ友への手紙
《速達の菊池》の若かりし頃の話です。
京都帝国大学の学生だった当時の菊池は、宮武外骨の日刊新聞『不二』の文芸欄に「草田杜太郎」の名で投稿しておりました。その文芸欄を担当していた石丸梧平(宗教家・小説家)はその原稿に共鳴を覚え、いつしか届くのを楽しみに思うようになります。日に日に語り明かしたい、という思いが募り、とうとう菊池の下宿先にまで訪ねますが、あいにく菊池は留守でした。手紙にその旨を書き送ると、菊池からすぐに返事が届きました。
「(前略)あなたがわざ/\私をお尋ね下さつた御親切は私の決してdeserveしないところです。それに私がどんな人間であるかを実際ご覧になつたら、あなたの幻滅の悲しさは、それはまあどんなであらうと私の方が怖れるのです。(中略)私は耽美主義者で、美しさを愛します。その私がみにくいと云ふのは私自身です。私自身の存在が苦痛です。
トルストイのお母さんは、トルストイに「トルストイや、誰もはお前の顔のためにお前を愛するものはないからお前はお行儀をよくして人に可愛がられなければいけないよ。」と云ひました。私は、それを聞いた多感なトルストイの心にしみじみ共鳴し得る男です。顔の為めに愛する者はないと云ふことは、どれほどたよりないことでせう。(中略)
私はあなたに逢へなかつた失望も、あなたの心にある私の幻想を傷けなかつた喜びに比ぶれば、何でもないと思ひます。どうかあなたのお心のうちにある草田杜太郎に、お手を触れないで下さい。(後略)」
(石丸梧平宛ての手紙 1914(大正3)年3月25日付け) その後もやりとりは続きますが、石丸が会いたいと伝えれば伝えるほど、菊池は心を閉ざしていきます。紆余曲折あるも結局、二人は一度も会わぬまま、絶交状態になりました。
その後、1919年の春に二人は、文士が一堂に集まった出版記念会で思いがけず対面することになります。石丸は、文芸雑誌の写真で菊池の容貌を知っており、そのため会場にいた菊池に気がつくことができました。石丸は声をかけますが、菊池は石丸とわかると沈黙し、応えることなくその場を去ります。翌年の正月にも、岩野泡鳴の家で二人は顔を合わせました。その際も菊池が打ち解けることはありませんでした。かつて文学への思いや作品、手紙によって共鳴していた二人でしたが、現実の世界では完全に乖離してしまいました。
娯楽の世界に広がる自由
1921(大正10)年のある日のこと、将棋を愛好していた石丸は思い立ち、将棋の会を開くべく友人知人に案内状を送りました。この時、菊池にも葉書を投函します。これまでの経緯を辿れば、おそらく相当逡巡したはずです。招待したものの、来ないのも当然と思ったことでしょう。しかし、菊池はこの招待に応じます。当日、会場に一番早く到着したのは菊池でした。文学ではなく将棋が、凝り固まってしまった二人の仲を解いたのでした。
勝負事が大好きで、人気作家になってからは、囲碁や麻雀・競馬・卓球・ゴルフなど、様々なアクティビティに打ち込み、娯楽として世に知らしめた菊池は、子どもの頃からの生粋の将棋好きでもあったのです。
さて、将棋によって繋ぎ直されたように見えた二人の関係でしたが、その後にまた思わぬ展開を迎えます。
実は先ほど挙げた菊池の手紙は、石丸が主宰していた雑誌『人生創造』に無断で掲載されてしまうということが起きました。将棋の再会から4年後のことでした。
石丸がどのような思いでそうしたかは実際のところはわかりませんが、決して菊池を辱めたかったわけではないでしょう。むしろ、時代に勇躍する「時の人」になっていた菊池の、まだ知られていない素顔――あのような繊細な心を吐露する若かりし菊池の瑞々しい感性を、心境的に最も身近にいた者として誇りたかったのではないでしょうか。この手紙が公開されたことについて、菊池は『文藝春秋』に連載していた「半自叙伝」で、このように記しています。
「石丸君に出した手紙を、同君は先年私に無断で発表したが、冷汗ものだった。つまらない、イヤガラセをする人だと思った。全集に手紙などを入れるが、私は死後でも自分の手紙などは、発表して貰いたくないと思っている。」
(「半自叙伝(9)」『文藝春秋』1929(昭和4)年5月号) なんとも菊池らしい言葉です。もし、本当に嫌がらせと受け止めたならば、菊池なら水面下で戦ったことでしょう。ましてや自身の筆でなぞるようなことはしないはずです。
思い出し、言葉に残すことができている過去、それは、すでに十分に咀嚼できた感情、乗り越えたものであるといえると思います。
抱えていた苦悶を解消するきっかけとなった「娯楽」。それに伴う「楽しい」、「面白い」という高揚には、長年の心痛をも凌ぐ力があるということではないでしょうか。
人生には様々な楽しみと同時に憂節も発生しますが、私たちには趣味を見つけ没頭し、娯楽を楽しむ自由があります。一人で楽しむもよし、誰かを誘うもよし。お誘いの手紙が届いたら、参加する・しないに関わらず、声をかけてくれたその気持ちにきっとどなたも心が解かれるはず。
自分の心と照らし合わせて、今必要な「楽しさ」「面白さ」を探求し続けることができたら、多くの人々を魅了した菊池寛の遊び心に、少し近づけるかもしれません。
(つづく)

©2023 POSTORY
近藤さんより
「菊池寛の手紙の世界を表すに、ふと民芸運動の創始者・柳宗悦が想起されました。
柳が、日常の暮らしに宿る美しさを追求し、美は民衆の中にもあると説いたように、文芸を愛し、ある種軽視されがちな娯楽をより多くの人が楽しむことを最善とする美意識によって貫いた菊池。なんとも粋ではないでしょうか」
☆ 『もう一度読みたい文豪の手紙』 次回の更新日は7月23日です。第10回もどうぞお楽しみに! ☆
<参照文献>
『菊池寛全集』(1993-1995年 高松市菊池寛記念館)
菊池寛・菊池夏樹『菊池寛のあそび心』(2009年 ぶんか社)
片山宏行『菊池寛の航跡 初期文学精神の展開』(1997年 和泉書院)
小林和子『日本の作家100人 菊池寛 人と文学』(2007年 勉誠出版)
大西良生『菊池寛研究資料』(2010年 河端商会)
『新潮日本文学アルバム39 菊池寛』(1994年 新潮社)
【POSTORY】
https://postory.jp/