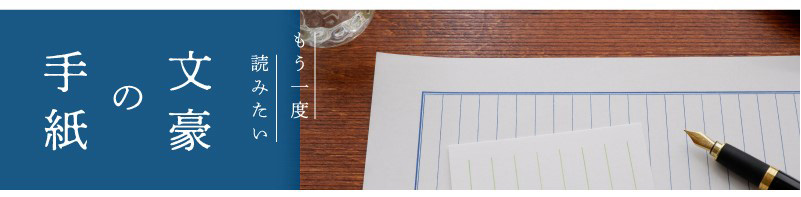1901(明治34)年に刊行した『武蔵野』を代表作とし、自然主義文学の先駆者として知られる詩人・小説家の国木田独歩。当時の文学青年のみならず、あらゆる知識欲を持つ人々に刺激を与えた人物です。そんな独歩は文学者として活動する一方、ジャーナリスト・編集者として生涯にわたり奮闘を続けた仕事人であったことをご存じでしょうか。彼がジャーナリストとして脚光を浴びた書簡の文体や、共に働く先輩や仲間に向けて書いた手紙にふれて、その仕事術と人生観をご一緒に学んでまいりましょう。
愛弟への手紙
1871(明治4)年に千葉県銚子で旧播州龍野(現・兵庫県たつの市)の藩士・国木田専八の息子として生まれた国木田独歩は、本名を哲夫といいます。幼い頃は亀吉という名前でした。
裁判所に勤務していた父の転勤先の山口県で育った独歩は、1887(明治20)年に16歳で上京し、翌年に現在の早稲田大学にあたる東京専門学校の英語科に入学します。政治家を志していた独歩は、在学中から雑誌に論説を発表していく一方で、キリスト教の教会活動にも熱心に参加する学生でした。独歩は、1891年に東京専門学校で起きた学生運動へ参加し、退学して山口へ帰郷します。大分県で教師生活を経て3年後に再上京します。そして、『文学青年』に参加すると共に、徳富蘇峰の出版社・民友社に入社しました。
その頃の独歩は、まだ国木田独歩の筆名を名乗る前で、本名の国木田哲夫の名前でジャーナリストの仕事をはじめます。その名を一躍有名にしたのが日清戦争の従軍記でした。
時は折しも1894(明治27)年9月半ば――民友社に入社直後の23歳の独歩は、海軍の従軍記者として軍艦に乗り、日清戦争の戦場レポートを『国民新聞』に発表します。この連載は冒頭や文中で「愛弟」と呼びかけるスタイルと書簡形式が特徴的で、たちまち評判を呼びました。のちに『愛弟通信』と改題されて出版されます。

国木田独歩の書簡形式の従軍記『愛弟通信』(国文学研究資料館蔵)
※全ての画像の無断転載を禁じます
このスタイル確立については、独歩本人が以下のように「波濤」の章で述べています。
「『如何に通信すべき』是れ海軍通信者なる余が最初の自問なりき。通信するは容易なり、其の法を選ぶは難し。」
レポートするのは簡単だけれど、その方法を選ぶのは難しい。どのように通信するべきかという、独歩の自問が始まります。
ちなみに、『愛弟通信』を書いた独歩には、実際に7歳下の弟がいました。その弟・収二も長じてジャーナリストになっています。二人は折に触れて、心を動かされるありとあらゆることを共有し合ったという、仲のよい兄弟でした。独歩は、『愛弟通信』のスタイル確立のきっかけになった弟の存在について、こう記しています。
「山を賞し、海を語り、軍艦の壮を羨み、月の夜に、星の夜に、詩情に、慷慨(こうがい)に、談論に、懐旧談に、将来談に、笑に涙に、田舎の山路に、都会の客舎に、凡てを共にしたるは実に吾が一弟にして、彼れの趣味は吾が趣味、吾が聞かんことを欲し見んことを願ふ事は彼れに於て亦実に然りし也。」
自由に語ることを欲し、愉快に語ってこそ、はじめて意図する通信になるとして、独歩は「どのように通信するべきか」の答えを導き出します。
「今後余の通信は凡て、『余が一弟に与ふるの書状』なるべし。
読者諸君、諸君も亦た諸君の弟若しくは兄よりの書状を読むの心を以て読まれんことを希ふ。」
戦場レポートの連載を「手紙」スタイルにしたことで対象が絞られ、輪郭が際立ちました。読者は兄からの手紙を読むように親しみを持って迎え、結果人気を博します。独歩の企画勝ちといえるものでしょう。
奮闘の日々のはじまり
独歩は、1897(明治30)年に初めて国木田独歩の筆名を用いて、短編小説「源叔父」を発表しました。1901年には、今日において独歩文学の金字塔と呼ばれる第一短編集『武蔵野』を刊行します。自然主義文学の先駆者として、独歩は文学の歩みを展開していきました。
一方で、ジャーナリスト・編集者として、奮闘の日々がはじまりました。民友社を退社後は、『報知新聞』の報知社や、『民声新報』の創刊計画に携わるなどジャーナリズムの世界を渡り歩きました。独歩は引っ越しも繰り返していますが、不安定な経済状況での転居は望むものばかりではなかったことでしょう。
『武蔵野』の表紙画を描き、校正にも協力した旧友の岡落葉は、「この一箇所に定住せぬことが、独歩の作品に短篇の多い一原因になって居りはせぬかと思う。独歩の短い生涯はまことに忙しかった。天才者は短い時間に天から与えられた仕事を成し遂げるというが、独歩なども最初から三十八年間にあれだけの仕事をするように生れ付いたものという気がする。」
(「国木田独歩の身辺」)と記しています。
独歩が結んだ人との縁
転職を繰り返した独歩の人生でしたが、その中で結んだ人との縁は独歩の身を助けました。例えば、民友社で共に働いた竹越与三郎とは、職場が変わった後も以前と変わらぬ交流が公私共に続きました。6歳年長の竹越は独歩の心強い味方になりました。
竹越与三郎は、明治から大正、昭和戦前にかけて歴史家、政治家、ジャーナリストとして活躍した人物です。明治時代に文部大臣の西園寺公望の秘書官を務めたのちに衆議院議員となり、大正時代には貴族院勅選議員も務めました。そんな竹越を、独歩は自身と同じ民友社員、職場の先輩として慕っておりました。
以下の手紙の一文は、竹越が民友社を去った後に交わされたものですが、二人がいかに親しく交友を続けていたかを私たちに教えてくれます。
「拝啓
言ふも恥しき至りに候へ共小生夫婦も遂に離婚と相成り申候。(中略)小生今も尚ほ苦しくて/\てたまらぬ、しかしいくら苦しんだとて先方は何とも思はない。此辺が小生の馬鹿の馬鹿たる所以か。(中略)
恋! 女が男をだます美しひ名! こんな文字は字引からけずりたひ。(中略)」
(竹越与三郎宛ての手紙 年月日不詳・推定1896(明治29)年4月27日頃) この手紙には署名に「馬鹿者」とあり、宛名には「竹越君」と書かれています。離婚に際して苦しむ胸の内を語る独歩。いくら苦しんでも元妻はなにも思わないのだといい、自身の滑稽なありようを自虐しています。
この約1ヵ月後の手紙には、「馬鹿者」と落ち込んだ自身からの脱却を報告する手紙を送っています。
「小生は彼女の愛の冷却に由り却て自己の愛を一段高きに至らしめたるを信ずる也友愛をしみ/゛\と感じ申候。友あるものは幸なり。(中略)感謝致し居候過去は過去。戦ふべきは将来のみ。
君の今日までの友愛を感謝す、小生は復活したり。」
(同上 5月21日付け) 大きな喪失感のあとに、自身に寄り添ってくれる友の存在に気がついた独歩の、しみじみとした感謝が伝わります。感情の嵐を手紙に撒き散らしながも、友愛の幸せを思い出した独歩。過去と決別し、「戦うべきは将来のみ」と覚悟を決めたことを伝えるこの手紙からは、決意と同時に、支えてくれている相手に安堵してもらいたいという思いが感じられます。そして独歩のオープンマインドな様子が伝わってまいります。
自身の在り方としての美学
独歩のすごいところは、生活苦という窮地に何度立たされても、人を介し、巻き込み、決して身をやつさないことです。
独歩は、先述の離婚を経て再婚後、生活苦に陥っていた時代に友人の齋藤弔花、原田東風と鎌倉で共同生活を始めます。3人は財政上の困窮に苛まれながらも原稿を書き、出版社に売って生計を立てました。このとき独歩は「どうも斯う云ふ場合が一番大事である。困るからどうしても濫作することになるが、境遇に負けぬやうにせねばならぬ。」と言い、決していい加減な作品は生まなかった――そのように弔花は証言しました。これは独歩の美学と言えます。
美学といえば、果物は泉屋の上等でなければ、酒は京橋の加六のでなければ、足袋は銀座のどこそこのではないと履かない、というこだわりの一面もありました。
また、独歩は綺麗好きでこの時分でも石鹸は東京から取り寄せており、弔花の髪が乱れていると時々井戸端へ引っ張っていって洗いました。香水も常に絶やさず、死の床でさえも上等の香水を大切に使っていたと伝えられています。揺らぐことのない独歩自身の在り方を感じるエピソードです。
『婦人画報』の誕生
明治の黎明期に生まれ、近代国家の歩みの足音を背後に、ジャーナリスト・編集者として奮闘を続けた独歩の人生は、目まぐるしい社会情勢にも柔軟な現代のハードワーカーに比類するという見方ができるのかもしれません。
明治時代に内閣制度が創設されたのは、独歩が14歳の時。1885(明治18)年のことでした。独歩が18歳になった1889年には、大日本帝国憲法が発布されました。国会が開設されるなど、次々と近代社会の基盤が作られていきました。さらには、独歩が23歳の1894年には日清戦争が開戦し、その10年後には日露戦争という大きな国難がありました。
1905(明治38)年に講和が結ばれた日露戦争においては、未亡人が多数出現しました。日露戦争では戦死傷者、戦病者が共に22万人以上、双方合わせて44万人近い犠牲が伴われたのですから、伴侶や家族を亡くした人々はその人数以上です。日本においても自活の道を求めて女子職業教育の要望が高まった時代でした。
そのような世情のなか、1905年7月に創刊されたのが、独歩が初代編集長を務めた『婦人画報』でした。
独歩はこの翌年に独歩社を設立し、『婦人画報』のほかにも自分が手がけてきた『近時画報』など計5誌を引き継いでいます。そして、編集者・独歩が誕生させた『婦人画報』は今なお発行され、日本で最も歴史あるライフスタイル誌として多数の読者に支持されています。
独歩社を設立した1906年には、独歩の第三短編集『運命』が大きな脚光を浴びました。編集長、経営者として、そして作家として、まさにこれからという時が来たのです。
ですがその年の8月、健康を害した独歩は湯河原で1ヵ月ほど静養をしました。多忙を極める独歩の体は、すでに悲鳴を上げていたのです。翌年、独歩に肺病という診断が下りました。
自由の国・独歩社
独歩社は独歩を慕うメンバーで成していましたが、中でも吉江喬松(当時の号は狐雁。フランス文学者・作家)とその友人の窪田空穂(歌人・国文学者)、そして小杉放菴(当時の号は未醒。画家・歌人)は特に独歩を支えた人物です。
1908(明治41)年に独歩が没したのち、独歩社のメンバーたちは、独歩と妻・治子の合著『黄金の林』(日高有倫堂)を刊行しています。序文を吉江狐雁が手がけました。
「独歩社は自由の国であった。何人にも自由の発言権もあれば、仕事の上には如何なる自由活動も許るされていた。その自由の国の中で、皆な出来る限りを尽くして共に考え、共に憂い共に戦っていた。実をいえば私達は「社員」というような心持で仕事をしているのではなかった。友人の団体に仮りに「社」という名前を付けたものに過ぎなかった。極めて真面目にまた極めて呑気に働いていた。(中略)此集を見るにつけ、一層当時の自由の国が思い出され、統率者の高い高い真の人格を深く忍ばずには居られない。思う所は多い、が、今私はこれ以上言うことばを知らないのだ。」
(吉江狐雁の序) 独歩や社員はそれぞれ短気を起こしたこともあったでしょうし、ぶつかり合うこともあったでしょう。多彩な顔ぶれが集まっていた独歩社が孤雁のいうように自由の国であり、実際に自由を感じられていたのならば、それはひとえに独歩の采配と人間としての魅力にほかなりません。
日頃の関係をあらためて大切にしていく
1907(明治40)年の夏、独歩は医師に転地療養を勧められます。独歩の病は肺結核でした。夏の終わりに転地先から小杉未醒に宛てた手紙には、独歩のまっすぐな思いが綴られています。
「(前略)僕も少々悔しくなつて来た 今死んでたまるものかと思ふと涙がぼろ/\こぼれる。然し心弱くてはかなじと元気を出してこれから大に病と戦ひ遠からず凱歌を奏する積也」
(小杉未醒宛ての手紙 8月26日付け) そして1ヵ月後に送った手紙の末文がこちらです。
「(前略)君も気のクシャ/\する事があるだらう 僕もイラ/\することもある、けれど此美なる秋晴の面に免じて根性を横着に持たうではないか、所謂(いはゆ)る楽天家になりませうよ」
(同上 9月27日付け) この手紙の約8ヵ月後には独歩は帰らぬ人となります。当時、不治の病であった結核に臥す形で人生の秋を迎えていた独歩は、冬の訪れを予感したこの時期に、こうして親しい友人に気楽にいこうと言葉をかけていたのです。
日常を離れ無理やり仕事からも離れ、状況を客観視し、まるで未醒をなだめているような文章ですが、その実、自身に言い含めていたのかもしれません。
独歩は人生において窮地に立たされた時、以下の特質を発揮しています。
→人に頼る
→卑屈にならない
→気の合う人を絶やさない
つらい時はつい内にこもって人との接触を断ちたくなってしまいますが、独歩のように助ける力を持っている人を頼り、よいも悪いも共有できる友人たちと過ごす時間は人生の財産になります。もちろん、苦難がない方が望ましいけれど、有事の際にどなたに会いたいか、話を聞いてもらいたいかをあらかじめ考えておくのはよいかもしれません。日頃の関係をあらためて大切にできると思うからです。
最後に静養先の湯河原から吉江孤雁に宛てた手紙の末文をご紹介します。
「(前略)兎も角も僕の帰京するまで、クボタ君に、僕の社がイヤでないならボンヤリしてノンキにかまへて闘球(※ラグビーのこと)でも勉強して居給へと御伝言被下度候 湯河原も己にあきがきました、僕は働くがスキ也。」
(吉江孤雁宛ての手紙 年月日不詳・推定1906年8月末) 働くが好きなり。――決して順風満帆なだけではなかったはずの独歩の仕事人生は、本人のこの一言によって全肯定されています。独歩にとって、相手の肩の力を抜いてあげられるような楽天家の自分を貫くことも、大切な仕事の一つだったのかもしれません。
(つづく)

©2023 POSTORY
近藤さんより
「国木田独歩が初代編集長を務めた『婦人画報』創刊号の復刻版(日本近代文学館発行)です。当時も今も女性のエンパワメントに貢献する雑誌であることから、お茶をしながら思索を語り合うサロンのようなイメージで撮影しました」
<参照文献>
『底本 国木田独歩全集』(1978年 学習研究社)
福田清人・本多浩編『Century Books人と作品16 国木田独歩』(1966年 清水書院)
黒岩比佐子『編集者国木田独歩の時代』(2007年 角川学芸出版)
北野昭彦『国木田独歩 『忘れえぬ人々』論他』(1981年 桜楓社)
日本近代文学館編『復刻 日本の雑誌』(1982年 講談社)
江馬修『人及び芸術家としての国木田独歩』(1917年 新潮社)
【POSTORY】
https://postory.jp/