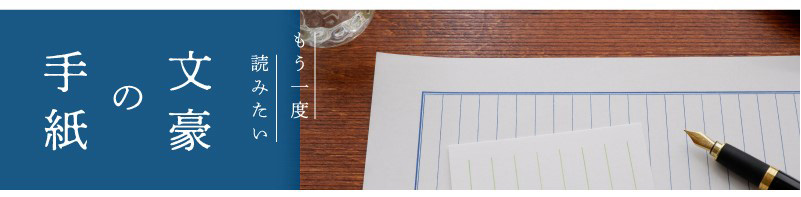第6回 文豪と文房具 -「書くこと」と文具をめぐって-
あなたは、大切な人の筆跡をご存じでしょうか。当たり前のように目にしていた身近な人の手書き文字ですが、今はその機会がずいぶん減ったように思います。書いた文字、それは例えば郵送される手紙に限らず、ご飯の献立メモや、連絡の走り書きなどにも表わされます。かつてよく見ていた文字は「鉛筆書き」、それとも「ボールペン」…? 思い返してみると、使用された筆記具にも懐かしさが漂います。
今回は、私たちが家族やパートナーの書く文字がどんな字形であるかを思い返すように、文学者たちの用いた文具や「書くこと」を振り返ってまいりましょう。
現代の詩人の愛用ツールは…
近代文学者が執筆するのに必要不可欠なもの、それは「書く」ための筆記具と原稿用紙です。
対して、誰もがパソコンやスマートフォンで文字を「打つ」のが当たり前となった現代。創作活動では、どのように執筆がなされているでしょうか。
今から遡ること約10年、2013年秋に六本木ヒルズで開催された講演にて、詩人・谷川俊太郎氏が、創作活動には筆記具を使わずMac(Apple社製コンピュータ)を愛用していると語っていたのが印象的でした。年齢に言及するのは野暮ですが、その時谷川氏はすでに御年82歳。「手書き」から「パソコン」へと「書く」ことが移行したのは、何も若い世代に限ったことではないという実感をもちました。
また、「書く」は「描く」と同義にもなり得ます。夏目漱石や武者小路実篤は、文学作品の他たくさんの書画を描き残しました。また、川端康成も見事な書を多数残しています。文豪それぞれの特色は手紙にも顕著に表れており、豊かな個性を発揮しています。
明治、大正、昭和の文学者は文学作品のみならず、絵画や書を嗜む傾向にあったようです。これは手書きが常であった時代だからこその、傾向の一つと言えるのかもしれません。現代の作家の中にも書画を愛好する方はたくさんいらっしゃると思いますが、自ら作品として仕立てる方はそう多くないのではないでしょうか。
明治時代の筆記具の変革
現代になるまで、日本文化の「書く」という行為に変革がなかったかというと、そうではありません。
例えば明治時代には、西洋の筆記具の移入がありました。まだまだ和紙に毛筆でしたためるのが一般的だった明治時代ですが、硬筆のための鉛筆、ペンとインク、万年筆の輸入と国産化の取り組みが進められていきます。
携帯するための筆記具として発展を遂げた万年筆の登場で、「書く」ことはより簡便に進化してきました。
毛筆も万年筆も存在するのが当たり前の現代から振り返ると、それほどのイノベーションを感じないかもしれません。とはいえ、インクで書いたものは正式な文書と見なされず毛筆がすべてであった時代、舶来品であった万年筆やペンの台頭は、人々に反発や憧憬、多様な思いを与えたであろうことは想像に難くありません。
漱石の万年筆観
万年筆、といえば夏目漱石を思い浮かべる方もいることでしょう。
1912(明治45)年、当時丸善(現・丸善雄松堂株式会社)に在籍していた翻訳家・作家の内田魯庵が、丸善の万年筆のPRとして漱石にエッセイを依頼したことがありました。
丸善とは、数々の文豪や芸術家が通った創業1869(明治2)年の老舗書店です。現在は丸の内に本店を置き、今もなおたくさんの人々が訪れ、知に触れています。
魯庵の依頼に応えて、漱石が書いたエッセイは「余と万年筆」というタイトルで、丸善の『万年筆の印象と図解カタログ』に掲載されました。全集などでお読みになったことのある方はお分かりだと思いますが、万年筆を使い始めた頃の漱石はそれほど万年筆に入れ込んではいなかったようです。
「自白すると余は万年筆に余り深い縁故もなければ、又人に講釈する程に精通していない素人なのである。」
(「余と万年筆」) と、肩の力が抜けた文章に親しみが湧きます。
魯庵から漱石へと贈られたイギリス製万年筆「オノト」は、漱石を敬愛する人々にとって憧れの対象になりました。「書く」という人間らしい知的な行為にさらに憧憬の要素が加わったもの、それが当時の万年筆だったのかもしれません。
憧れの暮らしを描いた鷗外の妻
漱石が丸善の万年筆カタログにエッセイを寄稿した年より2年前の1910(明治43)年、森鷗外は日本初の百貨店である三越呉服店の「流行研究会」会員に迎えられました。
三越はこの流行研究会(通称・流行会)に各界の学者や名士、文化人を集めて、研究を重ねるとともに、彼らにサロンの場を提供するという役目を果たしていました。大正3年には先述の内田魯庵も会員に名を連ねています。彼らが語るライフスタイルは、三越の新規市場・顧客開拓に直結していきました。
鷗外が会員になった翌年の1911年3月、月刊PR誌『三越』が発刊されました。その創刊号に鷗外が寄稿したのは「さへづり」という海外通信でした。鷗外は小説仕立てにした小文で、ヨーロッパ帰りの若い女性を主人公としたおしゃべり、さえずりを通して、ヨーロッパの最新ファッションや社会情勢を伝えています。創刊号には鷗外の妹・小金井喜美子の短編小説も掲載されました。
そして、翌月の誌面には鷗外の妻・森志げによる短編小説「チチエロオネ」が寄稿されています。タイトルは英語の「cicerone(チェチェローネ)」が元となっており、案内人や案内をすることを意味します。

森志げの『あだ花』。見返しには日本橋の和紙舗・榛原の千代紙が使われた(画像は森鷗外記念館(津和野町)所蔵書を原本に復刻されたもの)※全ての画像の無断転載を禁じます
志げのこの短編は、三越好きの主人公がいきいきとその魅力を伝えるところが特徴的です。主人公はピアノでシューマンを弾くことのできる、教養ある最先端の女性。表題の通り、この女性が三越呉服店(現・日本橋三越本店)の中を見物案内するかのように描かれています。華やかで文化的な生活を送るPR小説の主人公が明示するのは、当時の中産階級の人々にとっての憧れの暮らしでした。
志げは前年の1910(明治43)年に小説集『あだ花』(弘学館書店)を上梓しており、夫・鷗外の校正を受けつつ内なる自身の声を文字にしていきました。
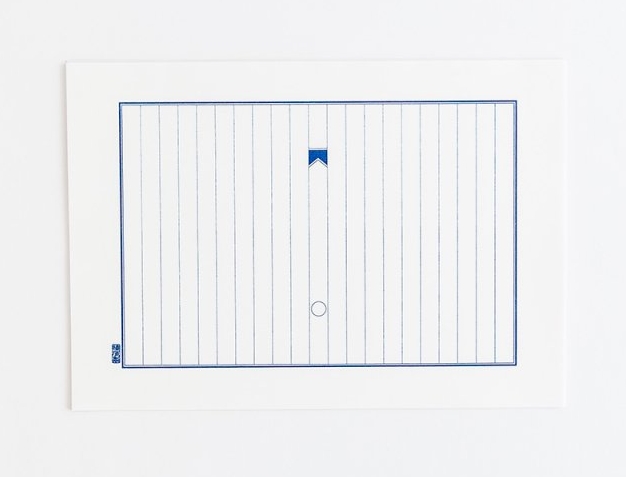
永井荷風は日記『断腸亭日乗』の清書に、榛原の「青色十行罫紙」を使用した(画像は復刻版「日乗箋」)
『あだ花』は、装幀布に志げが所蔵していた和更紗が使われています。見返しに使われた和紙は、榛原製のおしどり文様の千代紙です。榛原は日本橋にて1806(文化3)年創業、200年以上続く老舗和紙舗であり、その品々は当時の女性たちのステータスシンボルでした。志げのみならず鷗外、そして鷗外を生涯にわたり敬慕した永井荷風ら数々の文学者が愛用していました。
以上のように、文学者はある時には時代の先端に乗じて、自ら新しい流行を生み出す存在にもなり、理想の日々を社会に提案するオピニオンリーダーでもあったといえます。その活動にはいずれも「書く」ことが密接であり、かつ、人々の憧れを刺激するものだったようです。
読めない文字に出会ったら
話は変わりますが、展覧会で展示されている文豪の手紙、直筆原稿や掛け軸を前に、困った経験はないでしょうか。そう、「書いてある文字が読めない」現象です。躍動感ある運筆により文字がくずされ、その達筆な筆跡はくずし字を学んでいたとしても簡単には判読できません。日本語で書いてあるのに読めない事実に、中には恥ずかしく思う方もいらっしゃることでしょう。
川端康成や三島由紀夫、司馬遼太郎など様々な文学者と公私ともに親しくしていた故ドナルド・キーン氏がその著作の中で、読みにくい字は読めないことで成立しているという旨を表しています。
キーン氏は、ご存じのように外国出身の学術研究者として初めて文化勲章を受章した日本文学者です。ニューヨーク出身でありながら、亡くなる7年前に日本に帰化し日本人として晩年を過ごしました。日本出身者以上に日本を知り、20代の頃からすでにくずし字を解読できた日本文学者でも、読めない文字はあります。そんな読みにくい字を前にして、果たしてこれを書いた人は読んでもらいたかったのか、と疑問を持ち眺めるキーン氏。読めない文字は文字の持つ意味以上に、自身の感受性に委ねて「鑑賞」する美的なものでもあると残しています。そうであるならば、たとえ読めなくても、字体やそのものが発する雰囲気を感じ取ることも、一つの文字の読み方と言えそうです。
カリグラフィーを学んだスティーブ・ジョブズ
「TED」というカンファレンスをご存じの方は多いと思います。
1984年にアメリカで誕生し、テクノロジー(技術)、エデュケーション(教育)、デザインの3つの分野において実績を持つ様々なスピーカーによる魅力的なプレゼンテーションが紹介されてきました。インターネット上で動画が無料配信されており、世界中に多くの視聴者が存在する人気のコンテンツです。
TEDスピーカーの一人、アメリカの言語学者ジョン・マクウォーター氏が2013年のカンファレンスで登壇した際、「テキスト・メッセージが言語を殺す (なんてね!)
(“Txtng is killing language .JK!!!”)」というトークの中で「書く」ことについて印象的な例えをしていました。それは、人類の歴史を24時間とすると、「書く」という行為は23時7分、つまり1日の終わりかけと言えるほどに遅く生まれたものだ、ということです。
私たちは物心がついてからずっと文字を書いてきたはずですが、長い人類の歴史においてそれは極々後の最近のこと。しかしながらこの「書く」という行為があったからこそ、論理的思考が養われ、交流が活性化され、経済や文化の発展を促進してきました。その結果、皮肉にも手書きの機会は失われつつありますが、これもまた自然なことなのでしょう。
Apple創業者のスティーブ・ジョブズがカリグラフィー(書)を学んでいたことは、スタンフォード大学卒業式での、かの高名なスピーチで話したことでも話題になりました。スピーチからその部分を引用します。
「――当時のリード大学は、おそらく国内で最高のカリグラフィー教育を受けることができました。キャンパス中のポスターや引き出しのラベルが、すべて美しい手書きで書かれていました。私は退学を決めたことで通常の講義を受ける必要がなくなり、カリグラフィーのクラスを受講することにしました。(中略)それは美しく、歴史的で、科学では捉えられない芸術的な繊細さで、とても魅力的でした。」
(『Stanford News』(2005年6月12日)より筆者訳) Appleを創業し、パーソナルコンピュータ(個人のためのコンピュータ)という概念を創出して世界に普及させたジョブズは、まるで寄り道のようにカリグラフィーの技術と伝統を学んだからこそ、美しいフォントを持つ最初のコンピュータを誕生させることができました。
こうしてテクノロジーの進化も、世界も、いまだ「書く」という行為に大きな影響を受け続けているといえるのではないでしょうか。
自筆は肉筆とも言い換えられるようにとても身体的なものです。一人一人声が違うのと同様、筆跡も固有のもの。大切な内容には丁寧さを心がけて書くことが大事であり、書家を志すのではない限り、字形の上手い下手は気にする必要はありません。
「書く」ことが少なくなってきた今、手紙の存続の危機を唱えることもできますが、私がそうすることはありません。
知的好奇心を持ち、歴史に学び、言語を巧みに使用してきた文学者をリスペクトする人々はこれからも絶えず存在することでしょう。後世に残る作品を生んだ彼らの人間的な交流の証としての「手紙」に理想のコミュニケーションを見るならば、手紙を書く人は決していなくなることはないと思うからです。
(つづく)

©2022 POSTORY
近藤さんより
「森志げの生前唯一の単行本『あだ花』の見返しに使用された榛原製千代紙のおしどり。おしどり夫婦という語がありますが、もしかしたらそれこそが志げの憧れの証左だったのかもしれません」
☆ 『もう一度読みたい文豪の手紙』 次回の更新日は3月23日です。第7回もどうぞお楽しみに! ☆
■取材協力・株式会社榛原
<参照文献>
『私がわたしであること 森家の女性たち 喜美子、志げ、茉莉、杏奴』(2016年 文京区立森鷗外記念館)
『流行をつくる 三越と鷗外』(2014年 文京区立森鷗外記念館)
『万年筆の生活誌 筆記の近代』(2016年 歴史民族博物館振興会)
『森志げ小説全集』(2012年 森鷗外記念館)
ドナルド・キーン『日本語の美』(2000年 中央公論新社)
初田亨『百貨店の誕生』(1999年 筑摩書房)
John McWhorter“Txtng is killing language .JK!!!”,TED2013, April, 2013(2022年12月20日閲覧).
“‘You’ve got to find what you love,’ Jobs says”,Stanford News, June 12, 2005(2022年12月20日閲覧).
【POSTORY】
https://postory.jp/