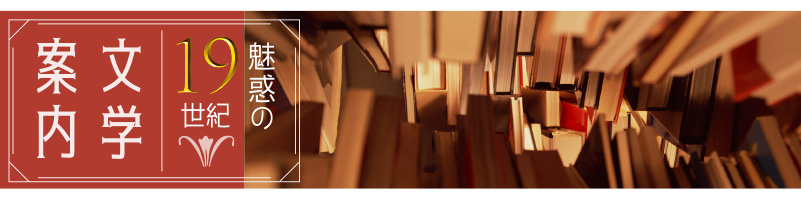第6回 「クオ・ワディス」 頽廃のローマに咲く愛と信仰の物語
あらためて言うまでもなく、ヨーロッパでは長年にわたってキリスト教が文化のあらゆるところに浸透し、強い影響を与えてきた。
前々回の「黒い蜘蛛」も、いま読むと疫病の暗喩としか思えないが、元来は人々を狙い、むしばむ悪魔の象徴だった。日本における仏教文学が、無常観だけは広く受入れられたものの、かならずしも主流にならなかったのとは対照的である。
ポーランドの作家、ヘンリク・シェンキェーヴィチ(1846-1916)の「クオ・ワディス」(1895-96)も、そんなキリスト教文学の傑作である。
舞台は紀元1世紀、皇帝ネロ治世下のローマで、小説「サテュリコン」の作者と伝わるペトロニウスや、ネロの側近だった軍人のティゲリヌス、あるいは十二使徒の一人である聖ペテロ、キリスト教の発展に多大な貢献をした聖パウロなど、実在の人物が多数登場する歴史小説でもある。西暦64年のローマ大火や、ネロによるキリスト教徒の弾圧といった実際の事件を扱いながら、架空のカップルのドラマティックな恋愛を絡ませ、史実の裏側を存分にさまようことができる。ありありと描き出されたローマ貴族たちの生活、キリスト教徒への激しい迫害、数々の困難が降りかかる恋愛の行方など、作品の湛える魅力は圧倒的で、ページをめくる手さえもどかしい。

イラスト:楓 真知子
主人公である若き軍人ウィニキウスは、招かれた家で異民族の王女リギアを見そめ、熱烈な恋心を抱く。相談を受けた叔父の廷臣ペトロニウスは、彼女を一度宮廷に召上げ、皇帝の口添えを得ることで思いを叶えさせようと画策するが、リギアは宮廷の放埒と頽廃に嫌悪感を抱いたうえ、酔ったウィニキウスから無理に迫られたショックで市中に姿を隠してしまう。彼女もまた自分を愛しはじめていたことをあとから聞き、後悔に駆られたウィニキウスは、キリスト教徒だったリギアが仲間に匿われていた場所をつきとめた。ところが、またもやその身柄を無理に奪おうとしたため、護衛の大男ウルススによって重傷を負ってしまうのだった。
保護されてリギアの看病を受け、またペテロの話に接するうち、ウィニキウスは自身の誤りに気づき、キリスト教の教えに心を傾けるようになった。ところが、芸術家を気取るネロは、業火を見たいというだけでローマを焼かせ、しかもその罪を着せたキリスト教徒たちを残虐な方法で処刑しはじめる。なんとか大火を逃れたリギアも収獄され、甥のために彼女の助命に奔走したペトロニウスは、かえってネロの不興を買うことになる。若き二人は死を覚悟し、キリストにすべてを委ねようと誓う…。
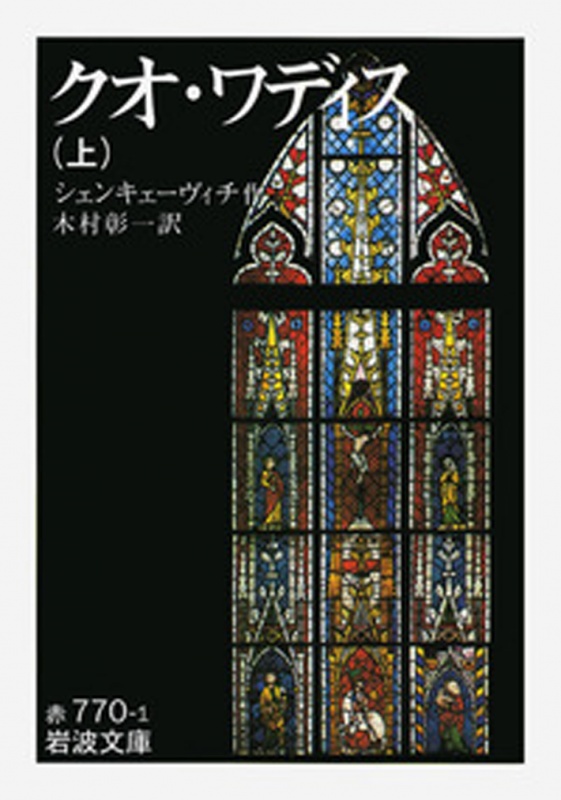
文庫本では上・中・下と3巻にわたる大作「クオ・ワディス」(写真は上巻)ヘンリク・シェンキェーヴィチ著(岩波文庫)
タイトルの「クオ・ワディス」とは、ラテン語で「どこへ行くのか?」の意で、ローマから逃れようとしたペテロが死んだはずのイエスに会い、「クオ・ワディス・ドミネ?」(主よ、どこへ行かれるのですか)と問うた場面による。復活の奇蹟に直面したうえ、「おまえがわたしの民を捨てるなら、わたしはローマへ行ってもう一度十字架にかかろう」というイエスの返答を聞いたペテロは、ローマに戻ってパウロとともに殉教した。この印象的なエピソードや、あるいは卑劣な哲学者キロンがパウロの憐れみを受けて改心する感動的な場面などを通じ、本作はキリスト教的愛の崇高さと力強さを高らかに謳いあげている。その意味で、本作がキリスト教文学の傑作であることは間違いない。
だが、この小説の奥深さは、最後までキリスト教に共感せず、ローマ文化の美意識に従って典雅に死に就くペトロニウスを、ネロに対するもう一人の勝利者として描いているところにある。ペテロがイエスと出会う劇的なクライマックスを打消すかのように、キリスト教では禁じられている自害を優美に描き出して終る本作は、いわばキリスト教を相対化する思想をあわせ持っているのだ。
そうやって一度キリスト教から離れて物語を眺めてみると、ネロの圧政と残虐な弾圧の背後に、18~19世紀のポーランドが経験した苛酷な歴史が透けて見えてくる。ロシア・プロイセン・オーストリア・ボナパルト朝フランスといった大国の間で翻弄され、激しい抑圧と幾度もの虐殺を経験したポーランド民衆への思いが、本作の緊迫感の根幹にあるのだ。困難に満ちた恋愛という魅力的なストーリーで読者を惹きつけつつ、ローマ文化とキリスト教というヨーロッパの二大文化を描き出し、さらに祖国の運命への悲憤まで盛込んでみせる。その手腕は、19世紀ポーランドが生んだもう一人の世界的芸術家、フレデリック・ショパンの音楽にも通じるようである。
と、難しいことを申しましたが、何よりもまずハラハラドキドキのロマンスから目が離せない。理屈ぬきで圧倒的に面白い一作なので、ぜひぜひご一読を。ただし、一つだけ注意。最初の50ページ、ことによると100ページくらいは、ローマ人の名前が覚えにくく、生活様式もわかりにくく、何度も挫折の誘惑に駆られますが、かならずかならず耐えてくださいね。その先には、他では味わえないすばらしい読書体験が待っていますから。(つづく)