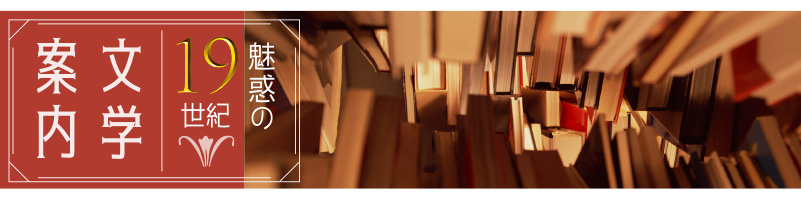どうもお暑うございます。
こうも暑いと恋しくなるのはやっぱり怪談!ということで、お化け書きの名手、泉鏡花の「星あかり」(1898)をご紹介しよう。
前々回、
前回ともに2分冊にわたる長篇だったので、今回はショート・ショートほどの読みやすい小品を選んだ。日清戦争期(1894-95)の文壇に華々しく登場してまだ数年、鏡花としては比較的初期の作品にあたるが、その怖ろしさは一級品である。いかに名作の多い作者とはいえ、これほどの優品があまり読まれていないのはいかにももったいない。
鎌倉の妙長寺に友人と寄宿している主人公は、夜の墓場を徘徊するうちに閉め出されてしまい、さほど遠くもない海端まで歩いてみようと思い立った。森閑とした深夜の道を歩いていると、ここにいてはならないような、身の置きどころのない思いに迫られる。由比ヶ浜に着いてみれば、どこまでも続く暗黒の水が怖ろしく、ついには大波に追われて寺まで逃げ帰ってきた。ようやく本堂に入り、蚊帳の片隅をつかんで覗きこむと、そこに眠っていたのはなんと自分自身であった。そんな物語である。
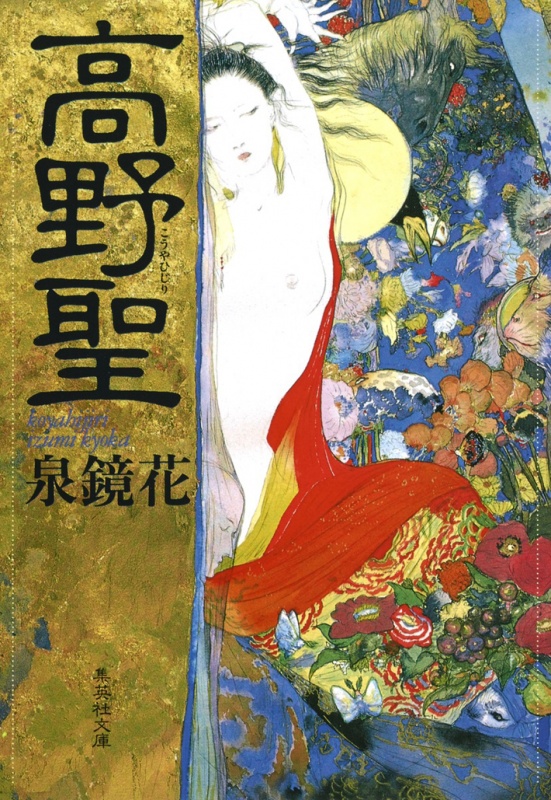
「星あかり」は「高野聖」に所収されている(集英社文庫)
読書経験豊かな方なら、ああドッペルゲンガーものね、と思われる向きも多かろう。ドッペルゲンガーとは自分自身の姿を見てしまう幻覚のことで、遭遇した人は近いうちに死ぬとも言われ、E・A・ポーの「ウィリアム・ウィルソン」(1839)が有名である。近代日本でも多くの作家がこのテーマを扱っており、鏡花の名作「春昼・春昼後刻」にも登場する。実は、和漢にも古くから離魂病という言葉があって、「星あかり」はむしろそちらの伝統に連なると言うべきだが、いずれにせよありがちな話に見えても無理はない。
だが、鏡花を見くびってはいけない。「春昼」の凄絶な不気味さは生涯の最高傑作との呼び声が高いし、本作もまた一ひねり利いて、仔細に読み返せばぞっとする怖ろしさにあらためて肌が粟立つ。以下、その一ひねりについてお話ししたいのだが、できれば本文を読んでからお聞きいただけるとありがたい。ご安心ください。
青空文庫※で手軽に読めます。
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
読まれましたか?
この作品の決定的に重要な点、それはドッペルゲンガーというか、あくがれ出た生霊というか、人ならぬ怪異こそが主人公になっていることである。最後の2段落に出てくる、友人と静かに寝ていたほうが真の自分なのは明らかであって、これはさまよう怪異を描いた物語なのだ。いやいや、離魂病にはそういう類話もあるよとおっしゃる方、ではここでもう一度考えてみてほしい。このさまよえる〈自分〉とは、はたして本当に自分の分身なのだろうか?
よく読んでみよう。たしかに〈自分〉は、友人の制止を振り切って夜の墓場に出たと言うが、なぜ閉め出されているのかわからないまま、卒塔婆をつかんだり、花筒の腐れ水を覗き込んだり、墓石に乗って雨戸を開けようと試みたりする。夜の道をゆくにも、「しおたれた、細い姿で、首を垂れて」ひそやかに歩き、「見られてはならぬ、知られてはならぬ、気取られてはならぬ」と身を潜める。犬の吠え声をはばかり、夜明けを避けるべく足を早め、寺に戻れば戸を無理に開けて瓦を鳴らしながら入り込み、蚊帳の外に立って中をうかがう……。これはどう見ても人ではなく、闇にうごめき、墓場をうろつく妖かしのふるまいにほかならない。

イラスト:楓 真知子
道中で行き会った荷車にしても、音もなくすべり、山道に入ってふっと消えたあたり、やはり人外の存在と見て間違いない。砂浜を暗い水に沈めた由比ヶ浜には、より恐ろしく強大な魔が棲むが、鏡花の描く怪異の世界は奧深く広がり、その姿を見定めることはできない。そうした恐怖に満ちた世界に棲む妖かしが、ふと人の世界に足を踏み入れ、寝ている男を自分自身だと思い込んでしまうとどうなるか。寝ていたはずの「自分」にその彷徨の記憶が乗り移った時、蚊帳の外に立つ何物かの姿はもう消え去っているとは、まさに人が妖異に憑かれた瞬間ではなかっただろうか。
では、最後、蚊帳のなかで「あたまがおもい」と言いながら母の名を念じている男は、自分の半身が妖異となったことにおののく、もとの「自分」なのだろうか。それとも……!?(つづく)