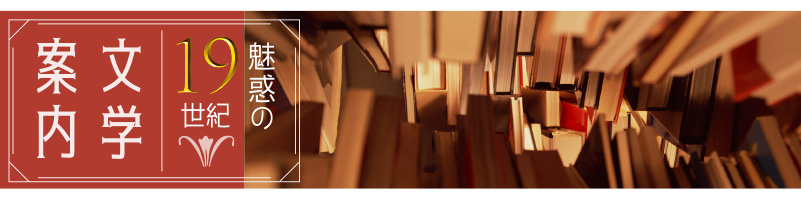最終回 19世紀文学の魅力 もう1冊読みたいかたに
19世紀文学は、なぜ面白いのだろう。
理由はいくつも挙げられるが、個人的には、何より安心して読めるというところが嬉しい。当時の認識はともかく、現代から見ると設定も展開も王道、いわばテッパンな作品が多く、やけに神経を遣ったり、不安にさせられたりせずに落着いて味わえる。20世紀以降の前衛性や尖鋭性を求める読者には物足らないかもしれないが、刺戟が過剰で難解な作品が続くと疲れてしまう身には、古すぎず、でも斬新すぎない19世紀文学はちょうど居心地がよいのだ。高度に知的な一部の読者だけを当てこむのではなく、広汎な読者を楽しませる姿勢をつねに持ちながら、でも相当な深読みや緻密な分析に堪える強度と芸術性を兼ね備えているところもいい。
日本では、樋口一葉や森鷗外、夏目漱石あたりがまさにそうだ。漱石が実際に活躍したのは20世紀はじめだが、ヨーロッパにおける19世紀文学的な概念は、本邦には少し遅れて入ってきたから、実質的には19世紀の掉尾と呼びたい。鷗外が歿したのは1922年、その翌年に関東大震災が起り、これをひとつのきっかけとして日本文学は急激に20世紀的に変貌していった。
もちろん、19世紀は明るいばかりではなく、現在につながる様々な問題が顕在化してきた時代でもあり、それらを捉えて現代にメッセージを送っているような作品もたくさん書かれた。そういう意味でも、19世紀文学を読むことには大きな意義があるはずなのだけれど、どうしても描かれている社会の時代色や文体の古風さ、忘れられた作品を再発掘する難しさなど、いろいろな事情から取上げられる機会が少ないようだ。これは日本だけのことではなく、2009年に英ガーディアン紙が発表した「誰もが読むべき小説1000作」(時代と言語不問、ただし長篇小説限定)でも、ラインナップのほとんどが20世紀の作品で占められていた。

イラスト:楓 真知子
そういうわけで、この連載のオファーを頂戴した時、はじめは古典文学全般というご提案だったのを、あえて19世紀に絞らせていただいた。こんな、そもそも読まれにくい時代を選び、テーマも言語圏もまったくばらばら、しかもメジャー作はあえて避けるなんていう、およそ通りそうもない企画にお許しをいただいた当コーナーには、深く感謝している。大長篇と掌篇が混在しているので、アンソロジーではなおのこと無理だっただろう。ただ、何しろかぎられた回数ゆえ、取上げたい作品をいくつも落してしまったのが残念で、この最終回ではもう1冊読みたいというかたに向けて、候補にあがった作品を簡単にご紹介してみたい。例によって、著名作はあえて略し、かつ何の一貫性もまとまりもないことだけはお許しを。
初回に書いたとおり大好きな英文学からは、候補作が多かった。エリザベス・ギャスケル「女だけの町」(1851-53、原題「クランフォード」)は、田舎町の人間模様が面白いが、「高慢と偏見」を優先してしまった。「ヴィネトゥの冒険」と重なるので落した冒険小説では、アンソニー・ホープ「ゼンダ城の虜」(1894)やバロネス・オルツィ「紅はこべ」(1905)、ジョン・バカン「三十九階段」(1915)が最高にわくわくする。動物愛護小説の先駆、アンナ・シュウエル「黒馬物語」(1877)もいいし、ミステリ寄りではウィルキー・コリンズ「白衣の女」(1860)や「月長石」(1868)は目が離せない。E.M.フォースター「眺めのいい部屋」(1908)、ドロシー・L・セイヤーズ「ナイン・テイラーズ」(1934)、あとこれも心惹かれるイーヴリン・ウォー「回想のブライズヘッド」(1945)・「ご遺体」(1948、別邦題「愛されたもの」)あたりも検討したが、20世紀ということで略した。ディケンズ、トマス・ハーディ、ジョージ・エリオットなんかは有名すぎるので全部省略(再々、よく許していただけたものだ!)。

イギリスのテレビでドラマ化された「女だけの町」(小池滋訳、岩波文庫)

「紅はこべ」(西村孝次訳、創元推理文庫)は各国で映像化され日本では宝塚歌劇団が舞台化

「眺めのいい部屋」(中島朋子訳、ちくま文庫)は映画化されアカデミー賞も受賞した
おなじ英語圏のアメリカでも、やはり英国の香りがする作品に惹かれる。騎士の時代を感じさせるトマス・ブルフィンチ「中世騎士物語」(1858)は、学部時代に熱中して読んだ。有名なヘンリー・ジェイムズのなかでも、「ワシントン・スクエア」(1880)はもっと読まれてほしい。ヘンリー・ソロー「ウォールデン」(1854)とフランク・ノリス「マクティーグ」(1899、邦題「死の谷」)は、どちらも一般向けに楽しい!とはちょっと言いにくく、惜しみつつ割愛。スティーヴン・クレイン「青いホテル」(1898)は、ネタバレしないほうがよいと思って見合わせたので、興味があるかたはぜひ。ビアスを入れた関係で落したナサニエル・ホーソーンの怪奇幻想小説、奴隷問題を鋭く告発するハリエット・アン・ジェイコブズ「ある奴隷少女に起こった出来事」(1861)、20世紀に入るイーディス・ウォートン「イーサン・フローム」(1911)や「ローマ熱」(1934)なども惜しかった。ちなみに、この時期の米国女性作家では、「絹のストッキング」(1897、未訳)をはじめとするケイト・ショパンの作品をもっと翻訳してほしい。
各国こんな感じで書いてゆくときりがないので、あとは簡単に。
フランスでは、本当はベルナルダン・ド・サン=ピエール「ポールとヴィルジニー」(1788)が突出して好きで、ラクロ「危険な関係」(1782)がそれに次ぐが、いずれも18世紀ということで見送った。ピエール・ロティ「秋の日本」(1889)は、専門分野からのひいき目が入っているかもしれない。ドイツでは、「みずうみ」(1849)で有名なテオドール・シュトルムの「遅咲きの薔薇」(1859)が最もなつかしく思われる。ハインリヒ・フォン・クライスト、アルトゥル・シュニッツラー、ハンス・ハインツ・エーヴェルスなどの諸作も紹介したかったところ。
ベルギーのジョルジュ・ローデンバック「死都ブリュージュ」(1892)はまことに美しいが、これも有名なので見送り。一方、オーストラリアのヘンリー・ローソンの諸作は、余裕があればぜひ入れたかった。ロシア文学は有名作品しか読んでいないので、レフ・トルストイ「セヴァストーポリ」(1855)と「光あるうち光の中を歩め」(1887脱稿)を検討だけしたが、任にあらずと手を引いた。もっと読んでおらず、ペドロ・アントニオ・デ・アラルコン「三角帽子」(1874)くらいしか知らなかったスペイン文学では、何十年かぶりに連絡をくれた小学校の同級生の示教による、「怨霊の山」(1861)などグスタボ・アドルフォ・ベッケルの作品に驚嘆、この作家を見逃していた不明を恥じた。フェデリコ・ガルシア・ロルカの詩作は最高にいいが、活躍したのは20世紀。

落語の怪談噺として名高い「怪談牡丹灯籠」は歌舞伎でも人気の演目に
本来の専門である日本文学は、一般向けに絶対面白いと紹介する関係上、どうしても文語の作品、特に江戸期の作品が取上げにくくて少なくなってしまった。三遊亭円朝の「怪談牡丹灯籠」(1884刊)と「真景累ヶ淵」(1888刊)は読みやすいが、鏡花とかちあい、また知名度もあるので泣く泣く見送り。饗庭篁村「月ヶ瀬紀行」(1893)、松原岩五郎「最暗黒之東京」(同)、広津柳浪「今戸心中」(1896)、幸田露伴・堀内新泉合作「雪紛々」(1901)あたりは本当は紹介したかったのだが……このあたりについては、いずれどこかで書かせていただける機会もあるでしょう。
それではみなさま、またお目にかかれることを願っております。どうか、これからもよい読書生活を!!(おわり)