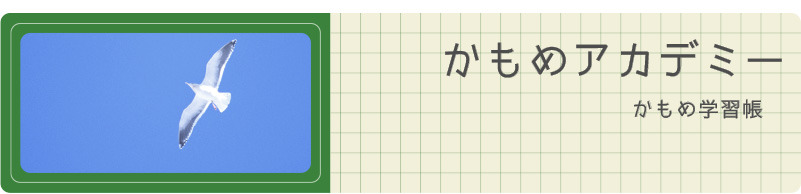第6回 ミストラル晩年の夢――アルル民俗博物館設立
ローヌ川の船頭たちは、偉大な叙事詩的民族である。〔漁師や船乗りたちが使用する道具のコレクションとその展示は〕、彼らの家の戸口や食卓で聴いているかのように〔生き生きとした〕、そして極めて綿密に研究された一つの作品です。 ――ミストラルからジュリエット・アダム宛ての書簡(1896年)より 1896年、その完成までに7年の歳月を費やした叙事詩『ローヌ川の詩』(Lou Pouèmo dou Rose、出版は1897年)の執筆を終えたミストラルは、プロヴァンス文化の継承および保存を目的として民俗博物館の創設を立案した。上述の言葉は、一連の詩作を連載した「ラ・ヌーヴェル・レビュー」誌の編集長に送られた書簡の一節だ。

ローヌ川から博物館までの道
今回は、晩年のミストラルが傾倒したアルル民俗博物館の設立の経緯と、そのコンセプトを中心に語る。個々の展示物については次回に紹介することとしよう。
アルルのコンスタンティヌスの公衆浴場に向かって北へ行くと、川辺にたどり着く。語らう友人や恋人たちにならって、私も護岸に腰掛けた。そよ風になでられながら、優雅に流れるローヌ川を見ていると、すっかり心の留め具が払われて、時間を忘れて自然の中に溶け込みたくなってしまう。しかし、いつまでもふけっているわけにもいかないので、その日の仕事を始めることにした。ここから徒歩でおよそ8分南下したところに、ミストラルが「プロヴァンスのパンテオン」と呼んだ博物館がある。旧市街のほぼ中央に、大きな門構えでたたずむ荘厳な建物で、中庭に古代ローマ遺跡群を抱えるようにして立っている。

アルル民俗博物館の入り口
ミストラルは自らを育てたプロヴァンスの生活文化・風習を忘れることなく、後世にその素晴らしさを伝えるために、この計画を思いついた。当初はアヴィニョン教皇庁内に美術品・書籍、コインやメダル、碑文などの考古・歴史・民俗学資料も含む広大な博物館複合施設を設立する予定であった。彼は1896年以来、この事業の成就に並々ならぬ情熱を注いだが、資金繰りなどが難航して、民俗博物館としての開設のみが叶うこととなった。彼にとって、場所は、何としても「アルル」でなければならなかった。それは、プロヴァンスの文化的特性を形づくる根底に「古代ギリシア・ローマ」があるからであり、二千年の歴史を伝える遺跡群が、19世紀においても――そして、現在においても――アルルの町を彩り、そしてその遺跡と歴史の延長にアルルの人々と町が息づいているからだ。

アルルのヴィーナス像
アルルの「古代ギリシア・ローマ」性を象徴するものの一つに、有名な「アルルのヴィーナス像」がある。1651年に発掘された立像は、紀元前4世紀のギリシア彫刻家プラクシテレスの作品と類似した様式美を感じさせる傑作である。実はこのヴィーナス像は、ルイ14世(在位1643-1715)の心をも射止め、一時はルーヴル美術館に展示されたこともあった。アルルの象徴がパリに移送されたことについて、ミストラルは中央集権的な権力への屈服だと嘆いた。現在では、ヴィーナスはアルルの地に再び帰り、人々を温かく見守っている。
ところで、博物館の創建を財政面で支えたのは、ミストラルが得た受賞金だった。1904年12月10日、ミストラルはスウェーデン・アカデミーから「地域の庶民の生活と自然をとても忠実に映し出した、極めて芸術的、天才的にして独創的である詩を考慮して、加えてプロヴァンス語の言語学の分野における重大な業績という理由によって」 、第4回ノーベル文学賞を授与された。ただし、賞はスペイン人の劇作家ホセ・エチェガライ(1832-1916)との共同受賞であった。
委員会が高く評価したのは、少数言語による文筆家としての活動に対してであった。なお、ストックホルムでの授賞式には両名とも高齢を理由に欠席した。それはともかく、フランス人としては2人目となる快挙は、74歳を迎えていたミストラル個人にとっての栄誉であるのみならず、「プロヴァンス」というローカルな枠組みの文学運動として軽視されがちであったフェリブリージュも、最高峰の権威による顕彰に浴したことで、その名が世界に広く知られる契機となった。
1906年、ミストラルはこのノーベル文学賞受賞金を運営資金として、由緒あるラヴァル=カステラーヌ宮殿を博物館の建物としてアルル市から4万フランで99年間借用する契約を締結した。既に1889~90年頃にその大半が執筆されていた『青春の思い出』が同年に出版されたのも、二分された受賞金の欠を原稿料と印税で補うためであったようである。建物の施設拡充と修繕、展示と準備が完了し、無事に落成式が行われたのは、まさに『ミレイユ』出版50周年に当たる1909年の5月29日のことであった。

アルル民族博物館の中庭。古代ローマの遺構が残されている
アルル民俗博物館(Museon Arlaten)は、「民衆」に主眼を置いた博物館構想としては斬新な試みであった。19世紀のロマン主義の潮流を背景に、地域文化の再発見と再発掘が国家主導によって推進された。目的は「上から」の国民的アイデンティティーの創造であり、さまざまな伝統と歴史、独自の言語を有する各地域を、「文化」の側面から国家の中に一元的に統合することに向けられていた。良く知られた例としては、フランス各地で大規模に展開された民謡調査が挙げられる。これに対して、ミストラルの試みは、プロヴァンスの地元の人々の手で民具を収集・保存し、日常生活に欠かせない身近な道具の価値を再認識することを目指すものであり、地域主導で実行された点がユニークである。
同時に、「歴史の世紀」と呼ばれる19世紀ならではの特徴もある。ミストラルとその共鳴者たちは、アルルの地とギリシア・ローマ文明の間に神話的な系譜を構築しようとしたのだ。既に18世紀の市当局は、共和政ローマ(前509〜44年)の標語で、「元老院とローマの民衆」を意味するラテン語のSPQR(Senatus Populusque Romanus)を、「元老院とアルルの民衆」SPQA(Senatus Populusque Arelatense)に置き換えて、自らの標語としていた。自らの歴史文化のルーツの淵源をはるかなる過去の歴史の中に追い求め、そこに「永遠の都ローマ」に比肩する、現在のプロヴァンス地域主義運動を正当化する根拠を見いだそうとしたのである。彼らを駆り立てたのは、19世紀における社会の急速な産業化を背景に、地域の伝統的な農村文化が変容し、やがては消滅していくのではないかという強烈な危機感だったのである。(つづく)
(写真提供:安達未菜)
*安達先生のインタビュー記事
「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は
こちら⇒