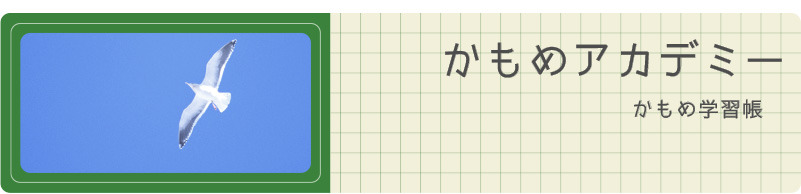第5回 ミストラル祭に参加して――マイヤンヌの「村おこし」

ミストラル祭での子どもたちの合唱
我々は 命尽きんとす
フェリーブル(※)が没すれば
我が同郷人も 果てゆくだろう
同じ根から生まれた
我々は 最初の若芽かも
祖邦(そこく)の 我々は
幹であり 頂芽かも
――「聖なる盃」(Coupo Santo)
※フェリーブル:フェリブリージュ(地域主義運動)団体の詩人たちのこと これは19世紀にミストラルが作詞・作曲した歌の一節。毎年、ミストラル祭の参加者全員で歌われる定番で、大学のプロヴァンス語カリキュラムの認可証取得試験にも出題される代表的な歌となっている。
今回のテーマは祭り。ミストラルの生誕(1830年9月8日)を祝うミストラル祭は毎年9月第1週、週末の3日間開催される。彼の生誕地であるマイヤンヌにとっては、村をあげての一大イベントだ。

マイヤンヌ楽団による演奏(中央広場)
アヴィニョンとアルルの中間に位置するマイヤンヌの主たる産業は農業。ニワトリやウマの鳴き声、草を食むウシの群れ、そしてウサギの飛び跳ねる姿は日常風景の一コマである。そのような田園風景の広がる、のどかな人口約3000人の村に、フランスの内外からフェリブリージュのメンバー、それに大勢のミストラルファンが押し寄せてくるのだ。コロナ禍が明けた2023年以来、私はこれまで3回参加する機会に恵まれた。ここからは、2025年9月5日~7日に行われた祭りの模様をお伝えする。

伝統楽器演者(ミストラル博物館)
今年の目玉は、中世にプロヴァンス語で愛を詠った吟遊詩人トルバドゥールに由来する伝統音楽の演奏会だ。特に印象に残ったのは、伝統楽器の木管フルートやタンブリネール(太鼓)に加え、19世紀の文芸復興期にリメイクされて生まれた各種の楽器や、弦付きのタンブリネールなどによって演奏の幅が広がっていたことだ。伝統は変わらないものではなく、個性の核を残しつつ、時代に合わせて変化していくのだ。現地の人々に受け継がれ、息づいている「生きる文化」を体験することができた。
この3日間、プロヴァンスには太陽のまぶしい陽光が降り注いだ。まるでこの特別な日に合わせてくれたかのようだ。
初日の午後は、村の中心部に位置するイベント会場のミストラル・センターで、ドキュメンタリー映画が上映された。隣町のタラスコンにあるサン=ガブリエル礼拝堂をはじめとするプロヴァンスの様々な歴史的建造物や、中等学校生向けのプロヴァンス語教育、声楽コンサートの模様が紹介された。

ダンスの輪に加わる(中央、青いワンピースを着ているのが筆者)
2日目の午前中は子どもたちによる合唱、お遊戯の披露。正午にはミストラル博物館で前述のコンサートが始まった。多様な管楽器、打楽器、フットパーカッション、足踏み式のアコーディオンが奏でる繊細なメロディで満たされたホール内は、ノスタルジックな中世風の響きに包まれた。
この後、私は子どもたちと木枝に穴を開けて作製した気鳴楽器で、冒頭で紹介した「聖なる盃」のメロディを口ずさみ、それから、恥ずかしながらフォークダンスの列に加わったのであった。
祭りのピークを飾る最後の日曜日。この日は終日、古書市とアルル民族衣装の展示・販売が行われた。ミストラルがその代表作『ミレイユ』で描写した民族衣装は、当時は民衆の普段着であった。しかし、今日では祭りの際にのみ着用される特別な伝統衣装である。上部でまとめた髪を囲むように装着する飾り帯、エソ(éso)と呼ばれる黒色の長そでの衣服の上に装着する白いレース、シャペル(chapelle)という名の絹製ショール、伝統的な柄の入った丈の長いスカートなどである。中には、繊細な模様の手縫い刺繍やレースで作られた高価なものもある。

アルル民族衣装を身にまとって(教会前)
私はまず、10時に教会で行われたプロヴァンス語のミサに出席し、80名ほど集まった参列者とともに祈りを捧げた。それから外に出て、カトリックの伝統的なプロセッション、すなわち祈禱行列を模した練り歩きが始まる。参加できるのは市の関係者とフェリブリージュのメンバーに限られるが、私は特別に加わることを許され、23年以降毎年参加している。中心部の主要な地点を通過した後、目指すのはミストラルの墓所である。
到着したのは11時半。墓所では、慣例に即してフェリブリージュの会長が演説を行った。今年のテーマはユネスコの世界危機言語アトラスについてであった。この墓所は、ミストラルが生前に建てた、高さ3.5メートルほどのルネサンス様式の美麗な建築物である。モデルとされたのは、16世紀後半に新旧両教徒が闘ったユグノー戦争の時代に、貧民や病人のための施療院を開設したプロヴァンスの敬虔なカトリック教徒の一貴族が、その妻に贈った「愛の東屋(パビリオン)」である。ミストラルはトルバドゥールの詩心に基づき、これを「愛の神殿」と呼んだのだった。

スピーチの様子(2023年)
次はお待ちかねの昼食パーティ! 場所はミストラル・センター。市長や関係者の挨拶、表彰の後、乾杯と続く。私は2023年にはおそらく日本人として初めて、スピーチを行う機会を得た。プロヴァンス農民の精神を映し出すプロヴァンス語に誇りを持つよう訴えかけたミストラルの演説を引用した。
その後に続き招待された食事会では、アペリティフにセリ科植物のハーブであるアニスを使ったパスティスを、食事に魚介のスープ、牛の煮込みとオリーブオイルで焼いたトマトやナスの付け合わせなどを、白・赤ワインとともにいただいた。どれも美味しい! プロヴァンスの伝統料理には、他にも、カマルグの水牛をオレンジの皮、オニオンなどと一緒に赤ワインに漬け込んだマリネや、ドーブといわれる柑橘類の皮を用いた牛の赤ワイン煮込などがあり、祭り期間中の野外音楽フェスにて販売されている。
16時から夜までは広場で打ち上げコンサート。伝統楽器を使った地元のロックバンド、バンドゥーラの登場。その大音響にはいささか閉口したが、地元の人々には大好評だったとのこと。それにしても、にぎやかで息つく暇もないほど忙しい3日間であった。
「ミストラル祭」の歴史は、1930年にアルルで挙行されたミストラル生誕100周年記念の式典にまでさかのぼる。オペラ「ミレイユ」の演奏には、実に1万5千人もの観客が押し寄せたという。古代劇場では8000人もの観客を前に「愛の宮廷作法」(Cour d’Amour)の公演が行われた。「愛の宮廷作法」とは、12世紀終わりにプロヴァンスとピカルディで生まれた、プラトニックな愛の作法の掟を定める一種の法廷劇である。
このときには代表作の主人公である少女ミレイユを彷彿させる「アルル女王」が初めて選ばれた。この伝統は今日まで続いている。彼女はリヨン産のシルクをぜいたくにあしらった装身具を優雅に身にまとい、凱旋さながらに古代劇場に入場した。傍には通称「馬の番人」、すなわち牛馬の群れを管理するカマルグ地方のマッチョな男たちが、三つ又の鉄製農具を振りかざして女王をエスコートした。このとき女王が身に着けたのは、Napoléonの頭文字である「N」の文字が刻まれた赤いサテン生地である。これは、1860年にアルルを訪れた皇帝ナポレオン3世の皇后ユージェーヌが、ミストラルが作った歓迎の詩「皇妃ユージェーヌに捧げる歌」に対する返礼として贈ったものである。アルルの市庁舎には、現在もなお、生誕100周年記念祭に際して制作されたミストラルの詩の一節を刻んだ銘板が飾られている。

祈禱行列を模して練り歩く。先頭から楽団、会長とアルル女王(2025年)
再び9月のマイヤンヌ。祭りは「ミストラル」の名を冠してはいるものの、個人の英雄賛美、あるいは「神格化」を意図したものではない。祭の場には舞台装置として視覚化されたミストラルが、たとえば彫像として登場することはない。あくまでもプロヴァンスの伝統文化を担う人々の絆を強め、同時に若者や子どもたちの次世代へと貴重な遺産を継承・発展させていくことがその目的である。マイヤンヌの「村おこし」にも一役買っていることは言わずもがなである。(つづく)
(写真提供:安達未菜)
*安達先生のインタビュー記事
「プロヴァンスの言葉が伝える幸せのかたち」は
こちら⇒