
3回呼ばれたら旅をする、と決めている。
たとえば、火というキーワードがなんとなく脳内を漂っていた時期のこと。はじめて扉を開けた夜のカフェで、窓ガラスや鏡が反射する無数のろうろくのゆらめきに迎えられて、蜜柑色の美しい炎が強く印象に残った。
その翌日に書店でなにげなく雑誌を手にとり、ぱっと開いたページに、愛媛の内子町の和ろうそく作りが紹介されていた。これが1回目である。
2回目。終電を逃してタクシーに乗ると、ラジオが歴史的町並みの保存について話していて、内子町の名前が何度も発音される。
翌週、雑貨ショップで神保町の喫茶店のマッチ絵を思わせる燭台を見かけてのぞきこむと、内子町で手作りされたものという説明書きがあるではないか! さあ、これで3回目。どうやら内子町に呼ばれているらしい。愛媛のガイドブックを1冊買い、とりあえず宿と移動手段の予約をしたら、あまり下調べをしすぎないように気をつけて出発する。
旅は、たまたま出会うものこそ大切なのだ。インターネットで検索すれば誰でも同じように膨大な情報を手に入れられるいま、本当に意味があるのは「出会いかた」ゆえ、出発前からすでに旅したような気分になるほど情報を仕入れては旅の醍醐味が薄れてしまう。
されど、そんなふうに呼ばれて出かけた旅先に何があるのか、何を得るのか、じつのところ私にはよくわからないのである。運命の人や運命的なものに邂逅するわけでもないし、自分がとつぜん素敵に生まれ変わったりもしない。ただ、日常よりも少し注意深く目や耳や鼻を尖らせながら歩きまわるせいで、一瞬の美しい風景が身体に焼きつけられ、その断片が数えきれないほど体内に蓄積していくだけである。
旅に即効性はないのだと思う。何年もあとになってから、日常生活のふとした拍子に、内子町の宵闇に浮遊する蛍の群れや、宿の人が手で1匹捕まえて私の手のひらにのせてくれたこと、囲った両手の親指のすき間から見える薄緑の光の明滅が、いっきによみがえってきたりする。
あのとき、闇に漂う蛍の淡い光は古い時代の人々の魂のように感じられた――そう人に話すと、日本人の感受性ははるかな昔から蛍を魂に見立ててきたのだと教えてくれた。
そういえば和泉式部の有名な歌「物おもへば沢の蛍も我が身よりあくがれいづる魂かとぞみる」は、蛍を自分の肉体からさまよい出た魂と見なしていた。恋しい人への想いがつのりすぎて、うっかり体外へと遊離してしまった薄緑色の魂。
蛍がおしりにともす火。亡き人の魂。送り火。私の中で燃えている小さな火。旅のはじまりにあった火というキーワードは、再び螺旋状の円を描きはじめる。

イラスト:古知屋恵子
旅の目的地に関する本を読むには、予習型、現在進行形型、復習型の3つのスタイルがある。
閉所恐怖症なので飛行機が苦手で、海外への長時間のフライトには気晴らしとして必ずページ数の多い本を機内へ持ちこむことにしている。イタリア旅行のうち2度は現在進行形スタイルとして、塩野七生のイタリア随筆、村上春樹のギリシャ・イタリア紀行を携行したのだが、おまもりのような役割しか果たさず、ページを開いてもいっこうに頭に入ってこなかったから、結局はどちらの本もページの大半を帰国してから読むことになった。
私の性分にはそんな復習型の読書が合っているのだと思う。旅のあとでその土地にまつわる本を読むことは、心楽しい(もしくは苦しい)記憶の反芻と新たな発見の連続であり、10数年も過ぎてからの復習でさえ素敵な収穫がたっぷりある。
たとえば須賀敦子のエッセイに紡がれたイタリア人の夫との生活風景は、まったく未知のものだった。それは愛する書物について豊かに語り合いながらつつましい生活を送る文学者や編集者たちの日常であり、喜びよりは疲れと悲しみのほうが色濃く浮かびあがって見える庶民の生活である。
若いころに何度か須賀敦子の本を開いたことがあったのだけれど、どういうわけか読み進むことができずに数ページで閉じてしまっていた。まだ、機が熟していなかったのかもしれない。
それがいま、圧倒的な力をもって押し寄せてくるのだ。彼女の文章がたどる霧深いミラノや、石畳にこだまするヴェネチア人たちの鳥のさえずりのような声の抑揚や、彼女の夫が愛した詩人のゆかりの街トリエステの光が。
先ごろ京都のブックカフェで手にとった須賀敦子の本『塩一トンの読書』の最初のページには、こんな文章が綴られていた。
「ひとりの人を理解するまでには、すくなくも、一トンの塩をいっしょに舐めなければだめなのよ」
これは須賀敦子がミラノでイタリア人男性と結婚して間もないころ、姑が彼女に語ったという言葉である。姑も若いころに姑から聞いたのだといって、1トンの塩を舐めつくすほど長い長い時間をかけて、嬉しいことや悲しいことをともに経験することであると説明した。それだけの時間をかけてつきあっても、人間はなかなか理解しつくせるものではないのだと。
続けて須賀敦子はこう書く。「本とのつきあいは人間どうしの関係に似ているかもしれない」。
人間や読書ばかりではない。どうやら旅にも塩1トン分の時間が必要なのである。出発するたびに迷子になって、「どうして私はこんなところに」とブルース・チャトウィン風につぶやきながら、時間をかけてゆっくりと旅の時間を熟成させていく。本も旅も、自分の中で育てていくものなのだ。
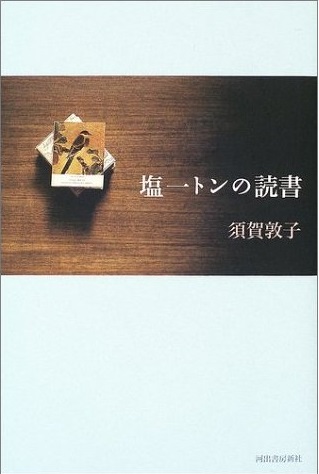
『塩一トンの読書』須賀敦子著(河出書房新社)
◇川口葉子さんのウェブサイト「東京カフェマニア」
http://homepage3.nifty.com/cafemania/

