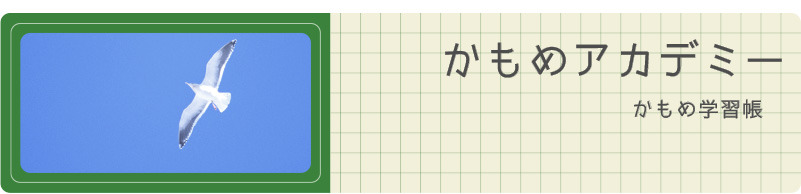最終回 新版歌祭文~野崎村 野に咲く花の恋と意地~お光ちゃんの選択?
うれしかったはたった半時 家にやってきた恋敵のお染に「ビビビビビ~!」とアッカンベーをしたオープンな性格のお光なのに、なぜ? ライバルを追い落とし、ようやく好きな人と結婚できるというのに、なぜ? どうして髪を切って出家なんかしてしまったのでしょうか?
「思ひ切ったといはしゃんすは、義理に迫った表向。底の心はお二人ながら死ぬる覚悟でゐやしやんす」
お染の妊娠のことを、お光は知りません。けれど久松と添い遂げようとするお染の必死さは、痛いほど伝わってきたのでしょう。他人に「あきらめろ」と言われて「わかりました」なんて、本心から言ってるはずがない、と。お父さんは自分にいいほうにいいほうにと捉えようとしてるけど、それ、違うから、と。お光は、現実をしっかりと見る子でした。
初めてお染を見たとき、「美しい……」とつぶやいたお光。顔では負けた。でも、私はちゃんと親から結婚の許しをもらっている! それがお光の誇りでした。だから勝てると思っていた。けれど、本当はわかっていた。久松さんの心はお染さんにある。負けたのは顔だけじゃない。
――本当はわかっていたの。最初から、私に勝ち目がなかったことは……。でも、祝言できるって聞いて、本当にうれしかった……。
「所詮望みは叶ふまいと思ひのほかの祝言の、盃するやうになって嬉しかったはたった半時。」
お染を追いかけてきた母の貞昌に諭されて、お染は母とともに舟で、久松は貞昌が乗ってきた駕籠で陸路、別ルートで大坂に帰ることになります。陸と川、別れ別れになりながらも、お染と久松は大坂に着いたらば、ともに死出の旅路に向かおうと、互いに目と目で確かめあうのでした。
そうとも知らず、お光は笑みを浮かべて二人を見送ります。自分の決断に悔いはありません。でも、彼らの姿が見えなくなると、こらえていたものが堰を切って溢れ出す。父親にすがって泣くのでした。
「道理じゃ、道理じゃ……」
久作はただ、娘を抱きしめるだけです。
この場面、初めはありませんでしたが、上演されるうちに「入れごと」といって役者が付け加え、それが定着して今に至ります。そうだよね。本当は悲しいよね。つらいよね。この幕切れには、観ている私たちも思わず熱いものが込み上げます。
身を引く=愛してない、じゃない! 歌舞伎はホンネが炸裂する芸術です。何も言えずに死んでいった人の悔しさを、観客は「口説き(くどき)」と呼ばれる長セリフを通して全部聞いてあげる。普通なら泣き寝入りするようなケースでも、歌舞伎では諦めず、艱難辛苦の末に敵討ち。あるいは幽霊になってでも復讐を遂げます。
でもそれは、「普通はできないことだから」お芝居になっている、という側面も否定できません。私たちには生活がある。人生がある。一瞬の感情で爆発してしまったら、次の日を迎えられません。だからこそ、フィクションでは非現実的なジェットコースターストーリーや爽快な勧善懲悪が好まれるのでしょう。
恋愛に限らず、職場に乗り込んだり刃傷沙汰になってまで、「絶対に渡さない」という壮絶な奪い合いは存在します。でも世の中の圧倒的の人々は、「じゃ、私はいいわ」とあきらめることのほうが多いのではないでしょうか。それが、常識の中で生きる、普通の人々の感覚です。
(あのとき、もうちょっと自己主張してもよかったかも)
(なんで追いかけていかなかったんだろう)
ときどき、そんな思いも浮かぶ一方で、考えに考えた行動だから自分の選択に間違いはなかった、と納得もしていることでしょう。
かつて生みの親と育ての親の間で、子どもの養育権を争った裁判がありました。「絶対に手を放さなかったほうが勝ち」と言われて両方の親が子どもの手を引っ張ったため、子どもは痛くて泣いてしまいます。それを見て、思わず手をひっこめたほうに養育権が与えられた、といいます。
お光の場合も、自分の気持ちだけでなく大好きな久松の気持ちを考えたら、ここは自分が引くのがいちばんいい、と考えたのだと思います。
愛する人を「手放した」かもしれない。でも、それは「ライバルより愛が少なかった」ということではありません。
身を引く女にも意地はある ここで、なぜお光は出家という手段にまで及んだのかを考えてみます。そんなことまでしなくても、単純に「私、あきらめます」でよかったのでは?
私は、これがお光の「意地」なのだと解釈しました。「出家」とは俗世を捨てること。恋だけでなく、人生を捨てる。死ぬことと同じです。お染が「添えないならば、死ぬ」という覚悟なら、お光も同じくらい、命がけの恋だった。でも、自分は死ねない。病気の母がいる。年老いた父がいる。だから俗世を捨てることで「この恋に人生を賭けていた」という自分の気持ちを形にして示したのではないでしょうか。
「野崎村」を観るたびに、私の脳裏には『木綿のハンカチーフ』という歌が浮かび上がってきます。1975年に太田裕美が歌ったヒット曲。歌詞は松本隆が書きました。
都会へと旅立つ恋人を、駅のプラットフォームで見送る女性。彼が「向こうに行ったら君へのプレゼントを探すよ」と言うと、地元に残る彼女は「欲しいものは何もないわ」と慎ましく答えます。願いはただ一つ、都会の絵の具に染まらないで帰ってほしいだけ。けれど祈り虚しく、やがて彼は「戻らない」決意をします。そのとき彼女は初めて「欲しいもの」をリクエストする。それが木綿のハンカチーフなのです。涙を拭くための。
若い頃、私はなぜ彼女が最後の最後にハンカチが欲しいというのか理解できませんでした。それも「涙を拭くため」という目的まで言うなんて、当てこすりもいいところです。けれど、今はちょっとわかる気がする。彼女は帰ってこない恋人をなじりはしない。都会にできたかもしれない新しい恋人とも、敢えて張り合おうとしません。でも、ずっとあなたが好きだった。ずっとあなたを待っていた。そのことまで否定されたり、忘れられたりしたくない!
いろんな思いを抱えながら、人はまた、同じ一日を繰り返す。そして必ず生きていく。当たり前の人間が当たり前に暮らすとは、そういうことです。自分の夢を追いかけるため、命がけの恋をつかむため、しがらみを捨てて家を飛び出したり、心中したり、そんなふうに飛躍できる人ばかりではありません。
お光ちゃんが、歌舞伎史上最も愛されるスピンオフキャラなのは、当たり前の日常を過ごす女性の胸の中の、「意地」と「涙」を描いたからではないでしょうか。
【仲野マリの歌舞伎ビギナーズガイド】
http://kabukilecture.blog.jp/【エンタメ水先案内人】
http://www.nakanomari.net
※WEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『恋と歌舞伎と女の事情』が(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)が好評発売中です。
新刊発売を記念して開かれた著者・仲野マリさんとイラストレーター・いずみ朔庵さんのトークショーの模様はこちらをご覧ください。

【なかの・まり】
1958年東京都生まれ、早稲田大学第一文学部卒。演劇、映画ライター。歌舞伎・文楽をはじめ、ストレートプレイ、ミュージカル、バレエなど年100本以上の舞台を観劇、歌舞伎俳優や宝塚トップ、舞踊家、演出家、落語家、ピアニストほかアーティストのインタビューや劇評を書く。作品のテーマに踏み込みつつ観客の視点も重視したわかりやすい劇評に定評がある。2013年12月よりGINZA楽・学倶楽部で歌舞伎講座「女性の視点で読み直す歌舞伎」を開始。ほかに松竹シネマ歌舞伎の上映前解説など、歌舞伎を身近なエンタメとして楽しむためのビギナーズ向け講座多数。
2001年第11回日本ダンス評論賞(財団法人日本舞台芸術振興会/新書館ダンスマガジン)「同性愛の至福と絶望-AMP版『白鳥の湖』をプルースト世界から読み解く」で佳作入賞。日本劇作家協会会員。『歌舞伎彩歌』(衛星劇場での歌舞伎放送に合わせた作品紹介コラムhttp://www.eigeki.com/special/column/kabukisaika_n01)、雑誌『月刊スカパー!』でコラム「舞台のミカタ」をそれぞれ連載中。