古くから日本の聖地で祀られている水の神、龍神。前回は、龍神信仰が黒潮に乗って海からやってきた倭人によって日本にもたらされたことを解説しました。今回は、龍の神が住むといわれる「龍穴」についてのお話です。 ※ページの最後にプレゼントのお知らせがあります。 日本列島でも海から川を遡って人々は移動していったわけです。川を遡って移動していって、水源近くの場所にその神の居場所を作っていくわけです。それが「室(むろ)」とか「岩屋」とか「岩戸」と言われている所です。「岩戸」とか「天岩戸(あまのいわと)」の「岩戸」という字を書きます。「室」というのは室生寺(奈良県宇陀市)の「むろ」、それから「御室(みむろ)の神事」という神事がありますが、御室の「むろ」も同じです。それから熊野と呼ばれる地域も和歌山県の牟婁(むろ)郡にありますね。どれも全部語源は一緒です。

川を遡って水源に達するという人々の移動、そして、水源から海に向かって川が流れていくというこの往復運動が、ぼくらの生命を根源から支えてきた運動ではないか、と考えられます。「室」とか「岩屋」とか「岩戸」と言われているところは日本中に分布していますが、では、それらを代表する言葉はいったい何かというと、ぼくは『日本の聖地ベスト100』(集英社新書)で書きましたが、それは「龍穴(りゅうけつ)」だと思うんですね。龍穴とか天岩戸とかどれも同じ意味で、龍神が住む場所という意味合いがあります。諏訪大社(長野県諏訪市)は龍神信仰の中心ですし、もちろん雨乞いでよく知られている室生寺もそうですし、室生寺は興福寺(奈良県奈良市)と繋がっていますから、興福寺もそうですね。京都の貴船神社(京都市左京区)もそうです。
そういうところには水の神が祀られています。朝廷が室生寺に雨乞いを年に二十何回遣わしたとか、これは文献に残っていますが、古代では貴船神社と室生寺は雨乞いでよく知られたところでした。それは龍との連想関係でつながっているわけです。
ちょっと映像で見ていただきたいと思います。4、5分ですが、室生寺の奥にひそんでいる龍穴を見ていただこうと思います。まず、学生たちをつれて歩いているシーンから始まります。最初に室生寺が映っていますが、それから、もともと室生寺が出来たきっかけとして、室生寺の奥に龍穴を訪ねるという流れになっています。そこまでの一連の流れを見ていただきましょう。

室生寺 写真提供:宇陀市商工観光課
室生寺は日本で一番美しいお寺と言ってもよいと思います。最初に山門を入ると鐙坂(あぶみざか)といって季節を彩るシャクナゲや紅葉が美しく映える階段があります。赤い傘をさして歩いているのが学生たちです。鐙坂を上がると、すぐに龍穴神社の遥拝所があります。それから軍荼利(ぐんだり)明王の石仏があって、金堂の須弥壇(しゅみだん)があるわけなんですが、そこにぼくが一番好きな十一面観音菩薩像が置かれています。金堂を過ぎると、日本で一番小さな国宝の五重塔があり、そして奥ノ院への階段へと続きます。そこまでが前篇で、室生寺を後にして、すぐ近くにある室生龍穴神社に向かいます。歩いて10分くらいでしょうか。でも、そこには龍穴はありません。そこから山の奥に車で分け入ることになります。

室生の龍穴 写真提供:宇陀市商工観光課
車で10分くらいでしょうか、まず天岩戸という岩が二つに割れている箇所があって、しばらく進むと「龍穴」という小さな看板がでてきます。これが信じられない気持ちのいい場所で、マイナスイオンが溢れているというか、小さな滝があって、水の流れがあって、特別な気配を感じさせるところです。こちら側に簡素な拝所が設けてあり、川の対岸に岩の亀裂があって、注連縄が渡されている。そこが龍穴なんですね。周囲の岩場には火山の噴火によるものでしょうか、柱状節理のようなきめ細かい岩肌が見えています。
龍穴と呼ばれている場所は、ほぼ100%聖地になっているというか、本来の聖地はことごとく龍穴がある場所と言ってもいいくらい。宮崎県高千穂町の天岩戸神社もそうだし、修験で有名な大峰山(奈良県南部)のてっぺんにもありますし、高野山(和歌山県高野町)にも龍穴があります。栃木県の日光にもありますし、木津川に沿って笠置寺(京都府笠置町)という寺があります。そこは、いまは千手窟(せんじゅくつ)と呼ばれていますが、かつては龍穴と呼ばれていました。
龍穴と呼ばれている場所は、龍神、そして雨の神様を祀っているところになるのですが、龍穴と呼ばれている所の地勢がわかってくると聖地の非常に古い形が見えてくるのではないかと思っています。

関東から木津川に行かれた方はあまりいないと思うのですが、京都と奈良の境を流れている川です。この木津川に沿って水の神様を祀る聖地が点在しています。笠置寺もその一つです。浄瑠璃寺もそうだし、海住山寺や、現光寺や、観音寺など、いっぱいあるんですが、それらのお寺の多くには十一面観音菩薩が飾ってある。十一面観音は、この木津川のほとりとか奈良盆地や琵琶湖の東岸などにいっぱいあるのですが、それらをずっと探して歩いたのが随筆家の白洲正子さんで、彼女は『十一面観音巡礼』というすばらしい本を書いています。この十一面観音と水の神の分布がなぜ重なるのか非常に興味深いところです。
木津川に沿ってずっとそういう分布があるのですが、一つずつ回って歩くとけっこう大変なんです。かなり高い拝観料をとられたりして。ところが、なんとこの間、京都国立博物館が、「南山城(みなみやましろ)の展古寺巡礼」という、十一面観音も含めて木津川の仏像たちが一斉に集められた展覧会をやってくれました。
ちなみに「龍とはいったい何なのか」ということですが、龍というのは日本では神話学的に蛇と一緒にされてしまうのですが、想像上の動物ですね。昔の百科事典によると、龍とは眼は鬼、耳は牛、鱗(うろこ)は魚、爪は鷹、手のひらは虎、角は鹿、とこう書かれています。これらがあわさったのが龍の姿だそうです。
※次回は、龍神を祖先に持つ人々について解説します。※この記事は、2014年6月7日に栃木県・那須の二期倶楽部「観季館」で開催された「山のシューレ」(主催:NPO法人アート・ビオトープ)の基調講演の内容を掲載したものです。「山のシューレ」は自然に耳を傾け、人々が創り上げてきたさまざまな物事について学び、領域を超えて語り合い思想を深め合う“山の学校”で、毎年夏に開催されています。
◇山のシューレ
http://www.schuleimberg.com/◇NPO法人アート・ビオトープ
http://www.artbiotop.jp/【プレゼントのお知らせ】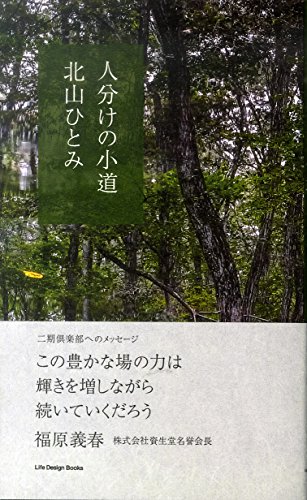
「山のシューレ」主催者代表の北山ひとみさんの著書『人分けの小道』(ライフデザインブックス)が発売されました。株式会社二期リゾート代表取締役社長で二期倶楽部支配人でもある北山さんが、リゾートホテルの新しい意味とかたちを求めた30余年の日々をつづった一冊です。
かもめブックスでは抽選で3名の方にこの本をプレゼントします。ご希望の方は、住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上、10月31日(金)までに下記アドレス宛てメールでお申し込みください。
※プレゼントは終了しました【かもめブックス・メールアドレス】
メールはこちらをクリック!


