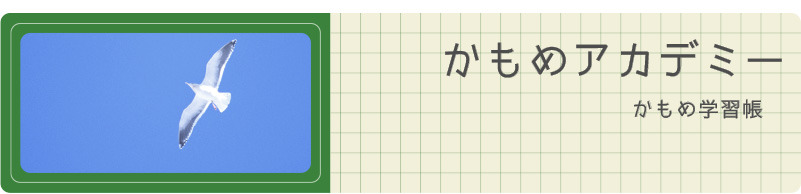近代建築の解体と壁面装飾の消失
本プロジェクトにケーススタディとしての意義を見出す背景には、日本全国に点在する多くの壁面装飾や貴重な近代建築が、老朽化などを理由に解体され、消失しつつある現状がある。解体を目前にした建築のなかには、小田原市民会館同様、壁面装飾があるものも少なくない。
1950年代末から60年代はじめ、つまり小田原の市民会館第ホールが建設されたころは、日本の公共建築に関する考え方が大きく変わりつつあった。戦前の市庁舎をはじめとする公共の建築の多くが重厚で威風堂々としていたのに対し、戦後は市民にとって開かれた場の創生が求められた。当時発刊された雑誌『公共建築』で新たに宣言された「市民のための市民広間」を目指す方針は広く共有され、市民のための建物はより開放的で、文化的で、開かれたものであるべきである、との議論と実践が活発化していく。建築空間の前庭には広場がつくられ、内部には開放的な空間が数多く設けられ、絵画や彫刻が置かれ、壁面には「壁画」が出現するのである。
たとえば1957年には、前川國男が自身はじめての公共建築として手がけた岡山県庁舎設計では、広場やピロティーを配して空間を外へ開き、同年に弟子の丹下健三が設計した旧東京都庁舎では「シティーホール」の機能を託した開放的な玄関ロビーを設けられている。翌年には香川県庁舎の壁面が猪熊弦一郎の壁画で装飾され、1959年に完成した横浜市庁舎の市民広間は辻晋堂のレリーフが壁一面に広がり、来庁者の目を楽しませていた。
とはいえ、最後に挙げた横浜市庁舎が2020年に閉庁し、ホテル等として保存活用された行政棟を除いて残部は解体された事例からも明らかなように、耐震性強化などを目的に戦後のいわゆるモダニズム建築が消失し、同時に内部壁面を装飾していた作品も姿を消す事例が近年は増加傾向にある。
2021年6月末に閉館した栃木県足利市の市民会館(1966-)では、日本劇場のモザイク壁画(一部が保存されたものの廃棄)を手がけた川島理一郎の手による緞帳と壁画の保存が検討されたものの、保管場所の確保の困難や、今後の活用方法を見出せなかったことなど、複合的な理由から廃棄されている。大阪のリバティおおさかでも、黒田征太郎が手がけた壁画《きずな》が解体され廃棄されたことは記憶に新しい。当初は移設保存が検討されていたものの叶わず、制作者の提案もあって作品の破片が市民に配布されている。
《赤い壁》《青い壁》の保存修復が進むなか、まるで双子のようによく似た発見経緯の物語をもつ作品が栃木県足利市に存在することを知ったのも、大きな驚きであった。1987年の北郷公民館建設時に制作された陶壁画である。公民館一階ロビーの壁を装飾する大作でありながら、いつのまにか備品が置かれ、全体像が隠れて忘れられつつあったものだ。地元の有志が調査と検証を進め、群馬県出身の彫刻家である田中栄作の作品であることを突き止めた。その発見のきっかけは、壁画前に置かれた家具で隠れていた右下の署名「EISAKU」であったという。
忘れ去られていた壁画、作品前に置かれた物品、隠された署名の発見──すべてが《赤い壁》《青い壁》の物語と重なり合う。熱心な調査チームの働きが功を奏して、2022年、陶壁画は改めて「作品」として一般に公開されている。
近代以降に建設された公共建築において、建物内部の壁面装飾はより自由な形や色彩の実験場として重要な役割を果たしてきた経緯があるが、上記からも明らかなように、たとえ保存活動が行われたとしても結局取り壊されたり、廃棄されたりする例が非常に多い。実際に保存や活用にまで道がつながるか否かは、行政の働きや美術館の協力、民間団体のサポート、あるいは保存のための資金繰りを算段できるかなどがターニングポイントとなる。
第2回展覧会の試み
全国でひそやかに消失していく壁画群のなかで、部分的に残すことができたもの、それが、《赤い壁》《青い壁》である。廃棄され失われていった数々の作品の命運を思う時、保存プロジェクトの意義が改めて立ち上がって見えてくるように思われた(図1)。
私たちは《赤い壁》《青い壁》保存修復プロジェクトを「こうしなければ残すことができなかった」事物と記憶のケーススタディとして一般に公開することを決定した。一部でも残すのであれば作品を切り取り「変容」させざるをえなかったこと、額装して「境界」を設けなければ安全に保管・展示ができる状態にはならなかったこと、よって壁面装飾を「作品」として展示されること──これらの問題をありのままに示し、批評を外に開くことをより意識した展示を実施したのが、第2回展覧会である(図2)。

図1. 小田原三の丸ホール 展示全景

図2. 西村による挿絵の原画

図3. 欠片の触覚展示
保存修復した作品を、プロジェクトの全貌を記録するパネルや部分拡大写真、調査報告などとともに総合的に展示する試みは第1回展覧会と同様であるが、加えて、西村保史郎という壁画の作り手の輪郭がより立体的に立ち上がるよう、西村が手がけた油彩画、挿絵の原画などを同時に展示し、さらには、剥離片に実際に触れて技法や構造を触覚から確かめる展示を組み入れた(図3)。全体を通じて、作品あるいは制作者をめぐる「語り」を同時多発的に行うことを意識し、作品のさまざまな記録/記憶のかたちをあるがままに公開するという姿勢を重視している。消失しつつある大壁画にまつわるさまざまな記憶は、パズルのピースのように会場全体に散りばめられており、鑑賞者は木立を歩くようにして、語り手の異なる記憶物の合間に遊ぶことができる。
100点の作品には、100通りの記憶の紡ぎ方が存在する。時間的な制約がなく、条件が整えば、《赤い壁》《青い壁》についてより良い処置を行うこともできたかもしれない。今回の保存修復の成果を展覧会の形で外部へと開いたのは、《赤い壁》《青い壁》の保存修復の終了を宣言するためではなく、むしろ継続的に批判的検証の対象とするためでもある。
時代が流れていくなかでひとつの建物が解体され、その内部にあった作品が共に消失することは、上述のようにそれほど珍しいことではない。ただ、消失の過程から何かを拾い上げ、記憶を繋いでいくことが叶えば、そこに一本の細道を残すことができる。たとえば50年後、あるいは100年後、誰かがもう一度、本展の記録や残された作品の断片から《赤い壁》《青い壁》に、あるいは小田原市民会館に出逢い直すことができるかもしれない。展覧会の主題「のこす つなぐ よみがえる」は、現在の時制を超えて、未来へ希望を託し名付けられたものなのである。
目にみえない実体を追いながら目に見える形におきかえること
プロジェクトに携わるなか、時おり思い出していた一節がある。1972年のイタリアの保存修復憲章第一項である。
「あらゆる時代のすべての芸術作品とは、広義において、建築から絵画、彫刻に至るまでの遺跡・記念物を指し、たとえ断片化していてもそれと見なされる」 断片化した作品もまた、芸術作品なのであり、それは保護され、保存されるべき対象なのである、という思想は、限られた方策のなかで残せるものを可能な限り残すことを試みた今回のプロジェクトのなかで、常に背中を押し続けてくれた。
もうひとつ、背中を押し続けてくれたものがある。他ならぬ西村保史郎の言葉である。
「絵描きは目にみえない実体を追いながら目に見える形におきかえるのが仕事」
「だから、無理押しでもうぬぼれでも自分の絵を描きまくらないと、ただの大法螺ふきの夢みる人にすぎません」 ※西村保史郎個展案内葉書より引用 (1988年3月28日-4月2日 於 資生堂ギャラリ ー)
西村保史郎の仕事と彼が残した痕跡の一部を消失させずに目に見える形でどうにか残す試みに励むなかで、西村の言葉が胸のうちにあり続けた。残すという選択をした以上、無理押しであったとしても、とにかく自分の仕事をしなくてはならないのだ、と。
《赤い壁》《青い壁》という稀有な命運を辿る作品の記憶を、今日まで、連載の読者の方々に、そして展覧会に来場くださった多くの方に見守っていただいた。作品の一部を保存し、プロジェクト全体の経緯を展覧会として一般に広く公開するという方法が、今も解体されつづける全国の建築物の内部装飾をめぐって同様の検討を続ける方々に、ささやかにでも役立てば、何よりの喜びである。(おわり)