世界各国を旅して出会った料理を“現地の味”にこだわって再現し、その国の文化や歴史までも紹介している「旅の食堂ととら亭」の久保さん夫婦。各国の特色あふれる料理のルーツを探ると、実は世界中の国々とのたくさんの共通点があることがわかる。地球上の人々は、食という文化を通じてつながっているそうです。――「旅の食堂ととら亭」は2010年3月3日にオープンした。そもそも、このお店を始められたきっかけは?
お店を始める前、僕は会社員として、妻はフランス料理の料理人として働いていました。もともと二人とも旅を通して出会いましたし、ずっと同じ場所にとどまって生きるイメージは持っていませんでした。そこで僕が会社員としてやるべきと定めていた目標がひと段落したとき、「自分たちが次に何をしたいか」「自分たちはこの先どうなっていきたいのか」ということを話し合い、そうこうしているうちに自然とこのお店を始めることになったのです。
――お店を始める前に旅したところも含め、これまでに訪れた国は46カ国にも及ぶ。店を始めてからも年に2回の取材旅行と1回の研修旅行に出かけ、その間の1~2週間は店を休む。6月下旬にも取材旅行で約2週間、ポーランド、スロバキア、チェコを訪れたばかりだ。 これまでに訪れた国の料理を調べているうちに、「次はこの国に行ってみよう」と思って旅先を決めることが多いですね。「旅の食堂」という店名にひかれて旅好きな人が自然と集まるので、お客さんから「旅先でおいしいものを食べたよ」といった情報をいただくこともあるんですよ。実はすでに取材先の候補が3年分ぐらいある(笑)。その中から第1、第2候補を選んで、最終的に現地の治安や国際情勢などを考慮して旅先を決めています。
――6月の取材旅行では3カ国を訪れたため、3種類のメニューを特集の料理として再現する予定だ。でも、旅先ではどんなレストランでどんな料理に出会えるのかわからない。
6月下旬に取材旅行で訪れたポーランドでの食事風景
旅のメニューは可能な限り、現地で僕たちが食べて「おいしい」と感じた味を再現するように心がけてきます。なぜならば僕たちの仕事は「情報を伝える」ことではなく、「体験を共有する」ことだからです。もしも日本人の口に合うようにアレンジしてしまったら、僕たちが旅で感じた「あの日、あの場所で」の感動が、「今、東京で」に置き換わってしまうと思うのです。
「料理」という世界の共通言語を通して体験の入り口まで案内することしか、僕たちにはできません。でも、情報と体験の境界が曖昧になりつつある今のこの国では、少なからず意味のあることではないかと考えています。情報と体験は量的にではなく、質的に全く異なるものです。そして、語り・行動する主体を最後まで裏切らないのは体験だけだと信じているのです。
――感動の味を再現するためにはお店の人から直接作り方を聞ければいいけれど、大概そうはいかない。 レシピ作りは僕の役目。旅行から帰ってきた後、取材ノートやレシピ本、インターネットの情報などをもとにレシピを作り上げていきます。それを参考にしつつ妻の智子が試作し、微調整を重ねながら現地で食べたものと同じ味を探していきます。
――たとえレシピが完成しても、料理はそう簡単に再現できない。ヒツジやチキンをヨーグルトで煮たヨルダン料理の「マンサフ」を作ったときにも、思いもよらないハプニングがあった。
チェコの首都・プラハにて
肉をヨーグルトで煮るだけの「マンサフ」は一見すると簡単な料理に思えるのですが、そのシンプルさゆえに極めて難解な問題にぶち当たりました。それは、ヨーグルトを分離させることなく肉を煮込まなければいけないという点です。でもヨーグルトは沸騰した瞬間に分離してしまいます。どうしたらいいのか?
本やインターネットで探しても、その解決策はどこにも書いてありません。材料のヨーグルトのメーカーを替えたり、文献をひたすら探したり、かき混ぜるスピードを変えたり……いろいろ試した結果、ようやく肉をヨーグルトで煮ることができました。
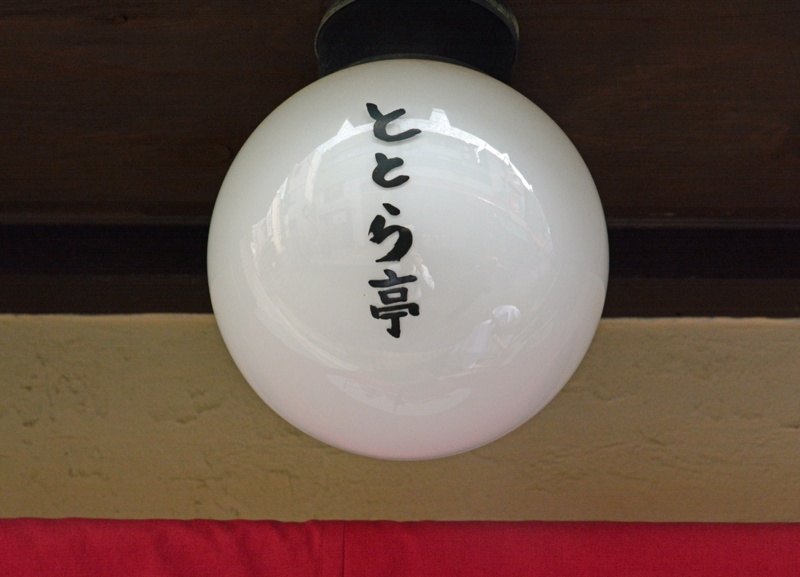
――取材旅行から帰るとすぐに料理を再現して紹介できるわけではなく、試行錯誤を繰り返し、同時に料理にまつわるルーツを探りながらメニューが作られていく。帰国してからメニューとして紹介されるまでにかかる時間は3カ月ほど。6月の取材分がメニューとして出されるのは秋ごろになる。どんな料理が食べられるのか? 次回(最終回)は久保さん夫婦が追いかける「世界のギョウザ」にまつわるお話です。(構成:山下あつこ)
【「旅の食堂ととら亭」のホームページアドレス】
http://www.totora.jp/


