「宇宙は何でできているの?」「私たちはなぜ存在しているの?」――。子どものころ、誰でも1度は疑問に思ったことがあるのでは? そんな壮大な謎に真正面から取り組んでいる東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)を機構長として牽引しているのが、日本を代表する物理学者の村山斉教授です。“現代のガリレオ”は、どのように育まれたのでしょうか。――村山教授の著作を読むと、宇宙やら素粒子やら難しい内容にもかかわらず、ユーモアあふれる言い回しについ笑ってしまう個所が多々ある。理解できたとは思わないけれど、面白いのだ。実際にお会いした村山教授は、さわやかな笑顔が明るい印象。きっと子どものころから元気で優秀なリーダー的存在だったんだろうなあ……と思いきや!?
夏休みの宿題の絵日記は、最後に慌ててまとめて書くような、どこにでもいる小学生でした。テレビもたくさん見ていましたよ。幼少期は喘息の持病があり、よく学校を休んでテレビをつけていたんです。昼間、子どもが見て面白いのは教育番組くらいだったのですが、高校数学レベルのものを落語を使って説明する番組をよく覚えています。「無限級数の収束」を長屋の八っつぁんと豆腐屋の会話で教えるとかね(笑)。
どんな内容かというと……
八っつぁんが豆腐を買いに行き、おまけをしてほしくてしきりに豆腐を褒める。すると喜んだ豆腐屋が、「よし、おまけだ持ってけ」と1丁を半分にしてタライに入れてくれる。もうひとこと褒めると、「よし、また半分持ってけ」と残りの半分を入れてくれる。もうひとこと褒めるとさらにその半分……と、延々と「残りの半分」をおまけし続けてもらうんです。
帰宅した八っつぁんは「しめしめ、だいぶせしめた」と考えるのですが、中を見るとたった2丁分の豆腐しかない。
これは1+2分の1+4分の1+8分の1……と無限に足していっても、その和は2にしかならないという数学の定理を説明しているのですが、これが非常に面白くて印象に残っています。無限なのに「答えが決まっている」というのがすごく不思議で新鮮に感じたんですね。こういう番組に接したのも、「数学は面白い」と感じたきっかけの一つだったのかもしれません。
――テレビ番組が数学を好きになるきっかけだったとは、意外なエピソードだ。村山教授を育んだ家庭、そして親とは、どんな存在だったのだろう。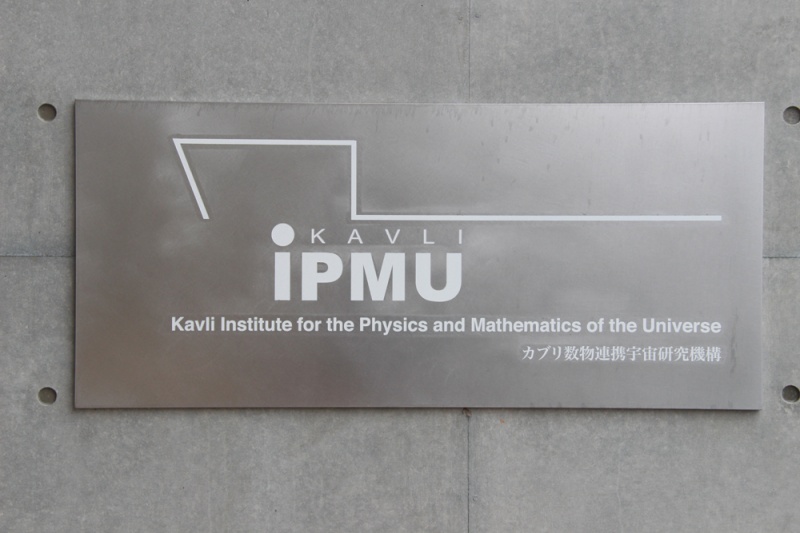
子どものころ、「勉強しなさい」と言われた記憶はあまりありません。父は半導体の研究者だったのですが、子どもの素朴な質問にもきちんと答える人でした。父に質問や疑問を投げかけるといつも答えが返ってきたのは、大きな刺激になったと思います。「疑問には答えがあるのだ」という、シンプルだけれど大切なことを学んだからです。
子どもはよく親に「なぜ?」という素朴な質問をしますよね。「なぜ飛行機は空を飛べるの?」とか「どうして空は青いの?」とか。でも、そういう質問はしばしば、「そんなことを考えてもしょうがない」「それはほかの人に任せて勉強しなさい」などと違う方向に向けられて中途半端に終わってしまいがちです。
けれどこうした問いにきちんと答えてもらえると、「ああ、この疑問には答えがあるんだ」ということが家庭の中で学べる。それはその後の思考力を育成するうえで、とても重要なことだと思うのです。
なぜかというと、それはやがて「答えがないという現実」に行き着くからです。
――「なぜ?」の地平の向こうには、「答えがないところがある」??? どんな疑問も答えがあると知ることで、解決したいという意欲も生まれる。やがて答えの先には、「現代の研究ではここまでしか解明されていない」という限界があることにも突き当たるでしょう。その「ここまではわかっていて、ここから先はまだ答えがない」という現実が確固としてあること、そしてそれに感銘を受けることは、とても貴重な体験です。そこから「この先は自分で解決してみよう」という意欲が芽生えるのです。
けれど、「ここまでは答えがある」というコントラストを明確にしないと、せっかくの疑問が何となく「答えはどうなのかなぁ」で幕引きとなり、解決意欲に結びつかないまま終わってしまいます。これでは残念ですよね。
これは、学問だけでなくビジネスでも同じではないでしょうか。グローバル化の中で日本企業も国際的な競争力のある新たなビジネスモデルや商品開発が求められています。今までの日本のやり方を知ったうえで、「ここから先は前人未到の地であり、新しい何かを考えなくてはいけない」という感覚を鮮明に持てることで、それを生み出せるのだと思います。
――父親の海外勤務で、11歳から14歳までの多感な時期をドイツで過ごした村山教授。帰国子女であることが、大学時代には大きな障壁になったという。
日本の社会には「言葉に出さないけれど、皆が心得ている感覚」のようなものがありますよね。たとえば年功序列のようなものです。そういうものが理解できず、「年上だから無条件に敬語で話す」「こちらが遠慮してへりくだる」などができないわけです。高校は帰国子女が多く学ぶ国際基督教大学高等学校だったので、「皆と同じじゃなきゃいけない」などと思うこともなくのびのびと過ごしていたのですが、大学に入学したときに“皆と同じ”を無意識のうちに好む日本社会全体を覆う感覚に初めて直面し、大きなとまどいを覚えました。ですから大学時代は「自分は周りから受け入れられていない」という疎外感が強く、とてもつらかったですね。
もともと音楽が好きだったので大学ではオーケストラ部に所属していましたが、授業も出ずに1日6時間ぐらい、楽器ばかり練習していました。今、振り返って自己分析してみると、楽器の演奏の価値は上手に弾けるかどうかという明確なものだったので、納得できたのだと思います。年功序列とか人間関係の微妙な背景は演奏には関係ないし、知ったかぶりをしながらクラスメートの話に合わせるより、ずっと楽だったんですね。
――こうして話している合間にも研究者が次々と訪ねてくる。彼らと流暢な英語で表情豊かに話す村山教授からは、ちょっと想像できない話だ。疎外感やつらさを切り抜け、現在の道を進むきっかけになったのは? 高校時代に滝川先生と出会って物理を好きになったように、大学時代もまた“出会い”に助けられました。私が特につらかったのは、やりたかった研究が物理学の世界ではすでに流行遅れで学ぶことができないと知ったときでした。「やりたいことがあるのにできない」という状況が納得できず、孤立した気持ちで悶々と悩んでいたある日、私を気の毒だと思ったのか、別の研究室の教授が私の関心分野の教授を外部から招いて集中講座をセッティングしてくれたのです。
それが現在、高エネルギー加速器研究機構にいる萩原薫教授との出会いでした。
その講座を受けたとき、「ああ、やりたかったのはこれだ!」と暗闇の中に光が見えました。そこで講座が終わるやいなや、萩原先生に「弟子にしてほしい」と頼み込んだのです。そこからは、とにかく行動あるのみでした。
その直後に海外赴任された萩原先生を3年間待ちながら、関連文献を片端から読み込みました。また、「一人の学生を指導するのでは効率が悪い」という先生の要望に添うために、日本全国を行脚して同じ志を持つ学生を7人集めました。ようやく目指す学問に取りかかれたのが、大学院に入って4年目を迎えようとする3月。論文を書く時間がもう1年もない時期になって、やっと基礎を学び始めることができたのです。それからは、がむしゃらに学びましたが、毎日がとても充実していましたね。
やりたいと思える目的がはっきりして、やりたいことがやれるというのは、本当に幸運で楽しいことなのだと実感する日々でした。

世界中から卓抜な研究者が集まるKavli IPMUでは、午後3時になると研究者たちが大きな吹き抜けになっている交流スペースに集まってくる。コーヒーブレイクを楽しみながら、数学者、物理学者、天文学者が日常的にコミュニケーションを図ることを意図したものだ。交流スペースの周りに階段状に設置されている研究室の扉もガラス張りで、部屋の内外で互いに声をかけやすい工夫がなされている
次回は、家庭で親が行う“働きかけ”について話してもらいます。


