「最近の子どもは体力がない」「だらだらゲームばかりして元気がない」……。そんなことを言われてもう久しく経ちました。「子どもの体力が低下している」と指摘され始めたのは1985年ごろ。もう25年以上も前のことです。そしてそれ以来、状況は深刻化の一途をたどっています。文部科学省が小中学生を対象に行う体力テストの結果でも、85年から数値は下がり続け、現在は下げ止まり。これは小中学生に限った傾向ではなく、6歳以下の未就学児にも共通しているという調査もあります。戦時下の食糧難時代ならともかく、なぜ豊かな現代に育つ子どもたちの体力が、こうも低下しているのでしょうか。そこには、基本的な動作の未習得と、運動量の減少という理由があります。
「遊び」の喪失が運動能力を退化させた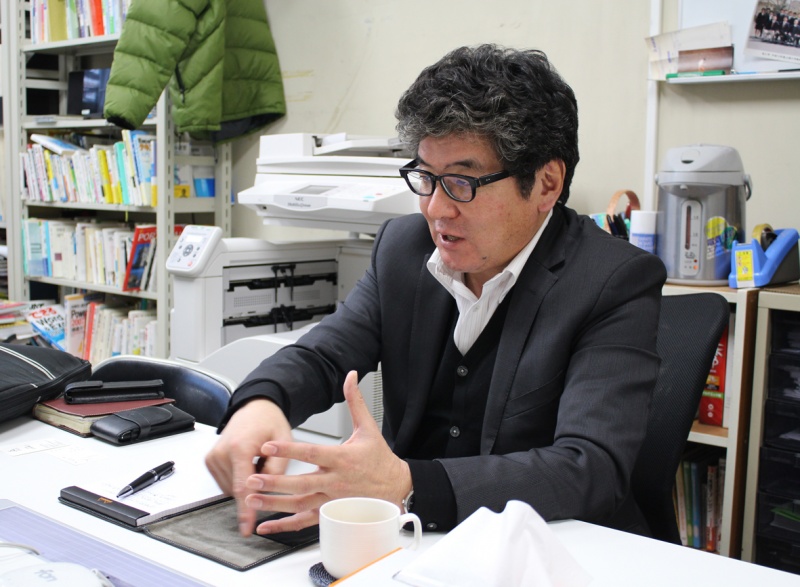
最近、小さな段差につまづいただけで転んだり、骨折などの大けがをする子が非常に多くなったことにお気づきでしょうか。また、まっすぐ走る、まっすぐ前転をするなどの単純な運動ができず、ラインやマットからはみ出してしまう子も大勢います。さらに手足で鉄棒にぶら下がる「ブタの丸焼き」ができない、縄跳びの前跳びができないという小学生もたくさんいます。
これらは以前なら遊びの一環として「普通にできていた動作」ですが、それができない子が増えている。子どもの運動能力がこの20年ほどで急激に落ちているのです。こうした子どもたちの姿に危惧する声は、教育の現場にいる先生方からも頻出しています。
遊びの一環として行っていた動作ができなくなった背景には、遊び自体が大きく変化したことがあります。今の子の遊びといえば、まずゲーム。体を動かさないゲーム一辺倒で、ひと昔前の子どもが当たり前のように熱中した三角ベースやゴム跳び、メンコ、缶蹴りや縄跳びのような遊びの体験は激減しました。
こうした遊びの変化が、子どものころに自然に身についたはずの「多様な動作」の喪失を生んでいます。走る、ジャンプする、投げる、蹴る、ケンケン、回るなど、さまざまな基本的な動作ができない子が激増したのです。
そして、この現象と二人三脚でやってくるのが「体力の低下」です。戸外で体を使って遊ばず、インドアでじっとしていることが多くなれば、当然、体力もつきません。子どもの歩行量の調査では、1970から80年代の子どもが1日あたり平均2万から2万7000歩も歩いていたのに対し、今の子どもは8000から1万3000歩と半減していることがわかっています。
さらに、体を動かさなくなると自律神経系が正常に機能しにくくなるため免疫力が弱くなり、感染症などに罹りやすいなど、虚弱になりがちです。
サッカーは得意なのにキャッチボールができない!? こうした子どもの変化に危機感を抱き、「子どもに適切な運動をさせよう」とする傾向も高まってきました。体操教室やスポーツクラブが盛んになっただけでなく、運動指導をカリキュラムに入れる幼稚園なども増えています。
けれど、これらの動きに私は疑問を感じてしまいます。確かに、体を動かす時間が増えるというメリットはありますが、はたしてこれで本当に、生きていくために必要な多様な動作が身につくのでしょうか。
最近よく、「サッカーは得意なのにキャッチボールができない」「野球クラブでは選手だけど、水泳の授業は苦手」などという子の話を聞きます。これは、幼児期に一つのスポーツだけを集中してやったことの弊害でしょう。決まったパターンの動作は磨かれていきますが、身体能力の基本を培うさまざまな動作を網羅して身につけることができていないのです。「サッカー教室に通っているけれど、それ以外の時間は塾とゲーム」では、いろいろな動きを経験できず、バランスよく運動能力を養うことができません。
(構成・株式会社トリア 小林麻子)


