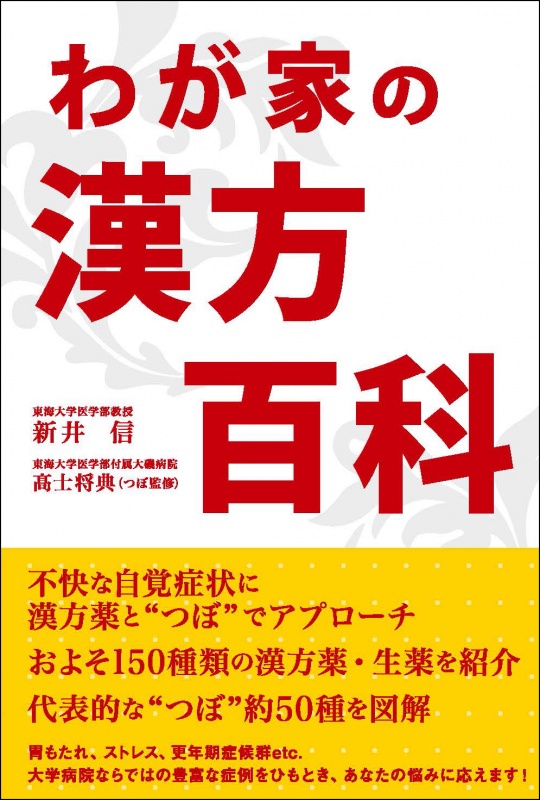
※このWEB連載原稿に加筆してまとめた単行本『わが家の漢方百科』が2017年4月に発売されました(発行:東海教育研究所、発売:東海大学出版部)。 漢方の治療はどのように進められるのでしょう。
漢方では、「四診(望診・聞診・問診・切診)」と呼ばれる方法で診察します。
それぞれ簡単に紹介すると、
「望診」=患者さんの容姿や動作、眼光、顔色、皮膚の具合、舌の観察など、視覚による診察。
「聞診」=声の明瞭さ、声の張り、問いかけに対する応答のほか、体臭や息のにおい、排泄物のにおいなど、聴覚と嗅覚による診察。
「問診」=病歴、自覚症状や訴えを聞き、医師が質問する診察。
「切診」=体に触れ、脈を診る「脈診」、腹部を診る「腹診」を主体とする診察。

患者さんが訴える最も不快な自覚症状を中心に据えて、これらの診察を通して病気にアプローチしていきます。
漢方の体系が出来上がった2000年も前には現代のような検査方法はありませんから、この四診を通して患者さんからなるべく多くの情報を引き出し、俯瞰することでその患者さんに相応しい処方を決めることが漢方治療体系の根幹となっています。
◆漢方治療の受け方にはコツがある 西洋医学では医師側からのアプローチとして病変部や検査値の異常などに着目し、血液検査や尿検査をはじめ、レントゲンや超音波、CTなどさまざまな医療機器を駆使して病気を診断します。その結果、たとえば抗菌薬などを用いて、それらの原因となる細菌やウイルスを排除することで治療をします。一方、漢方では患者さんのからだに着目し、自然治癒力を高めることによって病気の勢いを弱める、いわば患者側からのアプローチを重要視するのです。医師は正しい処方を導き出すために、どのような症状がつらいのか、さらに一見その症状とは無関係に思われる些細なことまで患者さんから聞き出そうとします。ですから、患者さんとの会話はとても大切なのです。
漢方の診察では患者さんの顔色や皮膚の色艶、張りなども重要な情報。ですから、女性はなるべくお化粧はせず、できるだけ普段のままで受診することが大切です。舌の状態をみる舌診もありますから、診察直前に色の付いたものを食べるのも避けましょう。
このように、西洋医学と診断治療体系が全く異なる漢方では、受診にもコツがあるのです。漢方の診療は医者に正確な情報を伝えるだけではなく、患者さん自身が自らの心身の状態を自覚し、病気を積極的に治すことにもつながり、結果的に治療の効果が上がるのです。
◆漢方治療であなたも変わる
漢方治療のメリットは、自覚症状の改善に優れた効果があること、病気の原因や病態が明らかでない場合でも治療が可能であること、漢方治療で期待していた症状以外の症状まで改善するなど、その利点はさまざまです。
漢方治療を受けることで本来持っている自然治癒力が高まり、体質が改善されます。体力がついてかぜをひきにくくなるだけでなく、気持ちも前向きになって精神的に安定し、健やかな生活が送れるようになります。これこそ、漢方の「心身一如」の考え方です。ですから、漢方治療によって結果として患者さんの生活の質の向上まで期待できるのです。
私は長年、漢方治療に携わっていますが、漢方治療で症状が改善した患者さんにはある特徴があると感じています。それは、治療を薬に頼りすぎることなく、自分の病気は自分で治そうと真剣に考えていることです。どのような時に症状が悪くなるのか、あるいはよくなるのか、自分で自分の病気を冷静に観察するようになります。
調子を崩す原因となっている生活習慣の乱れに気づき、それを改める。そして病気を治すために主体的に漢方薬を飲む。いったん症状が軽くなると心身にかかるストレスが減り、さらにからだ全体の調子が上がる。このように、漢方治療によって病気への取り組み姿勢が変わると治療は大きく前進するのです。それは本当の意味での“治癒”につながると考えてよいでしょう。
(構成: 編集部)
【東海大学医学部専門診療学系漢方医学のホームページアドレス】
http://kampo.med.u-tokai.ac.jp/

