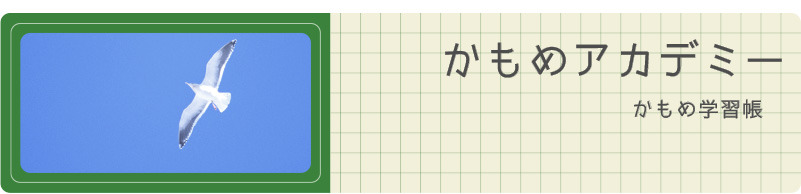自然の中で、町の中で、その土地の風土とともに芸術作品を楽しむアートプロジェクトが全国各地で開催されています。東海大学文化社会学部広報メディア学科講師の熊谷薫さんは、そうした地域のアートプロジェクトを支えるアートマネージャー。企画運営から広報、経理、振り返りまで「ある種のなんでも屋」と語るマルチな活躍で、各地にアートの輪を広げてきました。さまざまな人たちとの結びつきを軸とする活動は、時に地域や社会の写し鏡となることも。そこで、地域とアートの「これまで」と「これから」を熊谷さんにインタビュー。とりわけ私たちが大きな社会の転換期を経験する今、アートの自由な発想は、違った角度から未来を見つめるヒントをくれるかもしれません。
――各地で開催されている芸術祭やアートプロジェクトは、いつごろ、どのようにして生まれたのでしょうか?

熊谷薫さん
原点となるのは、海外で始まった野外彫刻などのアート活動です。「美術館ではない場所でアートを鑑賞しよう」という発想で、はじめは“作品を屋外に展示する”といったシンプルな試みから出発しました。1977年から開催されているドイツの「ミュンスター彫刻プロジェクト」は町の活性化を兼ねて始まったもので、町に作品を点在させる芸術祭の始まりとしてよく挙げられます。
野外展示に限らず、国際的なアートフェスティバルとなると歴史はさらに古く、「ヴェネチア・ビエンナーレ」は1895年発足と最も長い歴史を持ちます。ドイツのカッセルで行われる「ドクメンタ」が始まったのは1955年。ナチス政権時代を批判的に振り返り、新たな文化を考えるというコンセプトで、戦後ドイツのリブランディングにも関わる世界最大級の現代アートの祭典です。
こうした海外の動きを受け、日本でも「野外彫刻展や国際的な芸術祭を開催しよう」という機運が高まったのが1990年代。「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」や「横浜トリエンナーレ」は日本における最初期の国際芸術祭にあたり、それぞれ2000年、2001年に第1回が開催されました。地域に深く入り込み、現地のリソースに触れながら創造的な活動を行うことに面白みを感じるアーティストたちが増え始めたのもこの時期です。そこに、過疎化などの課題を抱え「何かしなくては」と考える地元の人たちの動きも重なり、地域を舞台にした小さなアートプロジェクトも実施されるようになっていきます。以来30年、大小のアートシーンは平行して発展を続けてきました。

©半谷学《風の龍:おとこ神とおんな神》2016年
「かがわ・山なみ芸術祭2016」

©六本木アートナイト実行委員会、越間有紀子「六本木アートナイト2019 インクルーシブ・ツアー」
昔はアートといえば「美術館やギャラリーで、アート愛好家のために見せるもの」という認識が強く、地域での活動に関心を持つアーティストは限られていたようです。また中心にあるのは大型の国際展、地域の小さなプロジェクトはその周縁といった関係性だったのでしょう。ですが、私の感覚ではここ10~20年でその“中心”はかなりずれてきている印象です。地域のアートプロジェクトが盛り上がりを見せ、そこから素晴らしいアーティストが数々生まれています。
作品制作にあたり、地域資源や地域が抱える課題などを綿密にリサーチするアーティストも多くいます。例えば、民芸や工芸に関心を寄せる現代アーティストの
遠藤薫さんの作品には、沖縄の戦後の工芸をテーマにしたものがあります。戦争によってすべてが破壊された戦後の沖縄では、何かを作るにも道具や材料がないため、あらゆるものを代用品として活用していたそうです。染色の道具として銃の薬きょうを使ったり、米軍のパラシュートの布地からウエディングドレスを作ったり。沖縄の複雑な歴史の中でたくましく暮らしを紡いできた人々の姿が、芸術や工芸に残されているのです。遠藤さんの作品には、そこから見いだした人間の営みや表現の面白さが反映されています。私も代表をつとめる
アートマネージャー・ラボという団体では、そうした魅力にひかれて、遠藤さんを含む3名の女性アーティストを招聘し展覧会を開催しました。

「Art for Field Building in Bakuroyokoyama :馬喰横山を手繰る」
2021年12月3日~12日、遠藤薫展示風景(主催:アートマネージャー・ラボ)
自分の足で現地をまわってあちこちリサーチしているので、本当に知識が多彩で驚きます。学者以上ですよ(笑)。それをアカデミックな分野とはまた違った、アーティストならではの表現で見せていくというのが非常に面白いですね。そういったアーティストはこれまでにもいたのかもしれませんが、発表の場は多くなかったのだと思います。
今は国内外を問わず地域の課題や資源を深くリサーチしたアート作品が増え、評価も高まっています。先ほどお話したドクメンタやヴェネチア・ビエンナーレなどは、多くの作家が非常に政治的なテーマを扱うので、世界中の社会課題をあらゆる角度から学べる場にもなっています。
――アートが「教科書に出てきたような名作を美術館で見る」といった枠を出て、私たちのような一般の人たちにも広がってくるような感じですね。地域アートの舞台で暮らす地元の人たちは、もともとアートが好きな方ばかりではないと思いますが、開催にあたってどのような反応がありましたか?
初期のころは特にそうですが、必ずしも皆が歓迎するわけではなく、反対意見が出ることも多かったようです。基本的にアートというのは異物であって、衝突や摩擦を起こすものなのですよね。それでも回を重ねるほど、アートに対する理解度は変わっていくように思います。
私は「大地の芸術祭」を見に行ったときに地元の観光タクシーを利用したのですが、運転手さんが作品についていろいろと話をしてくれたのです。「アートとかよくわからないんだけどね」と言いながらも、「この作品が好き」と自分なりの視点で批評しながら作品を説明したり、「この作品のアーティストは長期滞在していて、一緒に飲んだときにはこういう話をしていたよ」なんてエピソードトークをしてくれたり。もちろん開催を重ねても「やっぱり好きじゃない」と遠巻きに見ている人もいます。その一方で、積極的に巻き込まれてくれる人もいる。
アーティストとコミュニケーションを取って、さまざまな作品に触れる中で、作品のコンセプトを咀嚼して、自分なりの価値判断をするようになっていくのです。そうした変化もまた地域のアートを成熟させていく要因のひとつだと感じます。(つづく)
――アーティストも、地元の人も、変化しながら歩んできた30年。さまざまな人が関わり合い、地域のアートプロジェクトは独自の魅力を醸成してきたようです。そんな中で起こったコロナ禍という未曽有の事態。次回は、危機に直面したアート界で芽吹いた希望のお話です。(構成:寺崎靖子)