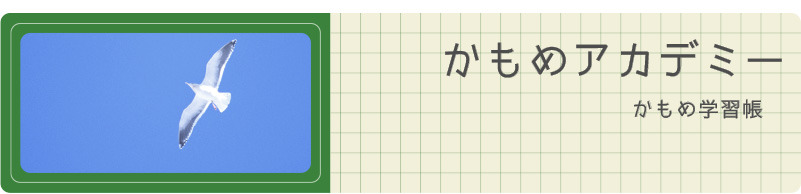調査、研究を重ねて芸術作品の「履歴書」をつくり、修復に生かしてきた田口かおり先生。2019年に開催された「印象派、記憶への旅」(ポーラ美術館×ひろしま美術館 共同企画)展では、ゴッホの作品について調査。さまざまな視点から研究した成果を展示でも表現しました。今回は、その過程での発見をはじめ、印象深い2つの展覧会について聞きます。
作品の“裏”が見えると面白い
「印象派、記憶への旅」展に先駆け、私はポーラ美術館所蔵のゴッホの3作品『アザミの花』『ヴィゲラ運河にかかるグレーズ橋』『草むら』について、2年かけて調査する機会をいただきました。特に印象的だったのは、『草むら』という作品です。現存するゴッホの作品の多くは、「裏打ち」といって作品の損傷を防ぐためにキャンバスの裏に第二の布があてられ、蜜蝋などで固められています。この手法は移動における作品の安全面が確保されたり、キャンバスの補強に役立つ半面、実はデメリットも多くあります。オリジナルの裏面が隠されてしまうことで、得られる情報が少なくなり、作品の来歴を知ることが難しくなってしまうのです。

ゴッホの『草むら』の裏面。裏打ちされていないキャンバスに絵具が付着している(提供・田口かおり)
ところが、『草むら』にはその「裏打ち」がされていませんでした。つまり、制作時に近い状態で作品が残されている、世界でも稀有な例だったのです。
キャンバスの裏には、“Vincent(フィンセント)”という書き込みがあり、タンポポが群生しているような丸い形状の黄色い絵具と、縦長の形状の緑の絵具が点々と付着していました。ゴッホは作品が完成するたびに木枠から外して絵画を何枚も重ね、グルグルっと丸めて唯一の理解者ともいわれた弟のテオに送っていました。そこから推測されるのは、キャンバスの裏面に着いた黄色と緑の絵具は、作品を重ねたとき下にあった別の絵画の絵具がまだ乾いていなかったために付着したのではないかということです。
そうなると次に、「下にあった絵は何だったのか」という疑問が出てきます。それがわかれば当時の作風や制作の順序がわかり、作品の輸送手段も改めて見えてくるかもしれません。そこで、世界中にある同時代のゴッホの作品をスキャニングし、『草むら』のキャンバスの裏にあった黄色と緑の模様をトレースして、ぴったり形状が合うものがあるかどうかを一点一点、照合していったのです。
残念ながら、一致するものは見つかりませんでした。『草むら』に付着している絵具で描かれた作品は、どこかに眠っている作品かもしれないし、すでに失われてこの世から消えてしまったものなのかもしれません。ただ、『草むら』を描いた当時のゴッホが庭の植生などをクローズアップで捉えていたこと、いくつかタンポポと思われる花々を描いていたことから、やはり黄色い花を中心に、草木を描いた一連のシリーズに属するものだろうと推測できます。
このように「裏打ち」されていない作品は貴重なので、展示でもポーラ美術館の主任学芸員・岩崎余帆子さんが一工夫。「裏が見える形で展示を」ということになり、360度回り込んで見られる透明な展示ケースに作品を入れて展示しました。調査で判明した成果などもパネルにして、ご覧いただけるようにしてもらいました。来場者の方々にも、珍しい展示形態、そして、ゴッホの「裏」を、面白く感じていただけたのではないかと思います。
刻々と変化する作品をリアルに体感できる展覧会
私は、あえて短命に終わるように制作されたものも含めた現代美術、パフォーマンスやいわゆる「インスタレーション」などにも着目し、どのような展示や保存が可能なのか、その記録の方法論も検討しています。

「タイムライン――時間に触れるためのいくつかの方法」展(2019年、京都大学総合博物館、提供・田口かおり)
そういう意味で印象深い展覧会は、同じく2019年に初めて私自身が企画側にまわった「タイムライン――時間に触れるためのいくつかの方法」展(京都大学総合博物館)です。現代美術の保存修復も手がけるようになり、時間の経過とともに変わりゆく芸術作品がたどる“生”の過程を浮き彫りにすることはできないか、と、若手の作家の方々と一緒に考えていた中で生まれた展覧会でした。
たとえば、𡈽方大さんの尿素でできている彫刻は、会期中に結晶化して、会期が終わるころには崩壊してしまう。いわばゼロから生まれて、変化を繰り返し、またゼロに近いところへ還っていく作品でした。あるいは、ミルク倉庫+ココナッツの作品の中では、生きているショウジョウバエが展示されていて、約2週間のうちに起こる孵化から死までの“生のサイクル”を目撃することが可能でした。そのような作品の「変化」の記録をいかに残すのか、ということを、展覧会という形をとって実験的に試みていく、というチャレンジングな企画でした。

同展で展示替えをする田口先生(提供・田口かおり)
この展覧会でどうしても作品に加えたいと思ったのが、井田照一さん(1941~2006年)が残した『Tantra(タントラ)』という402枚からなるシリーズ作品です。1962年から亡くなるまで40年以上にわたり継続的に制作された作品で、用いた素材は、庭で拾ったヤモリやヘビの抜け殻、ブルーベリージュースなど多種多様。特に病に冒された晩年の作品は、自信が咀嚼した食べ物や唾液、あるいは尿や血液などを絵具の溶液として用いるなど、一枚一枚が彼の日々の生活のあらわれであり、生の痕跡になっています。
数年前に作品の調査をさせていただいたことがきっかけで、研究を続け、経年変化を観察しています。素材によって少しずつ変化しているものもあれば、制作時の状態を保てずボロボロになっているものも。『Tantra』を間近に見るたび、そこに「時間」が流れているのだという確かな実感を得て、現代美術の作家がどのような素材を選択しコラージュしていくのか、色々調べ考えました。「時間の経過」をテーマにする展覧会を開催するなら、この作品群は外せないだろうと思ったのです。
最初はたまたま調査の過程で出合った作品でしたが、調査や修復を通して心惹かれ、研究の対象となって、そこから『Tantra』に関する論文を書き、展覧会にまで広がったというのは、私にとって初めての経験でした。こうした取り組みが、今後も続けていけたらいいなと思っています(おわり)
―― 会期中に崩壊してしまうような、特定の時間軸を持った現代美術の作品には、美術館を劇場に変える不思議な魅力がありそうです。直近では2019年から20年にかけて札幌、名古屋、大阪を巡回したイタリアの巨匠、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョの展覧会においてコンサベーターを務めるなど、精力的に活動する田口先生。展覧会の楽しみ方の一つとして、「正面からだけでなく、色々な角度から、異なる光の効果を使って作品を見ては?」と提案してくれました。異なる光――とりわけ斜め方向からの光は、絵画の描画技法を調査したり、作品に欠損や傷やあるかどうかを見つけるための調査方法の一つですが、時に展覧会場でも、作品の下にもうひとつ別の絵がある様子が画面の隆起した様子からうっすらとわかることもあるのだそう。変わりゆく作品の、歴史の一部に触れることができるかもしれませんよ。(構成・宮嶋尚美+編集部)