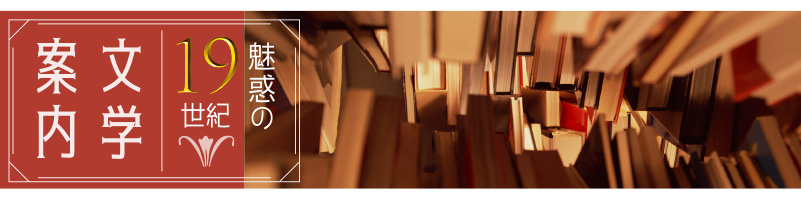第10回 「コールター・ノッチの戦い」凄惨な死戦の裏側に
インディアン戦争さえまだ続いていた北米で、アメリカ最大の内戦、南北戦争(1861-1865)が勃発した。背景にあったのは南北の経済や社会構造の相違で、特に奴隷制をめぐる対立が知られている。しかし、奴隷解放宣言を出して人道的なイメージのあるリンカーンが、同時にダコタ保留地で暴動を起したスー族に対し、一度に38名もの絞首刑執行など苛酷な弾圧を行っていたことは、米国における人種問題の複雑さと根深さを物語る。
そうした意識や切迫度の差を反映してだろう、インディアン戦争が長いこと西部劇風の描写に終始してきたのに対し、南北戦争は早くから様々に描かれ、いくつもの傑作を生んだ。戦争中における南部の白人社会を描いた、マーガレット・ミッチェル「風とともに去りぬ」(1936)はその代表作である。当然、戦闘そのものも題材とされ、鬼才スティーブン・クレインは無名の一兵士の視点から、挑戦的な名作「赤い武功章」(1895、「赤い勇気の勲章」の題で新訳あり)を書いた。そしてもう一人、アメリカ戦争文学の名手として忘れてならないのが、「悪魔の辞典」で知られるアンブローズ・ビアス(1842-1914?)である。
オハイオ州に生れたビアスは、南北戦争に際して北軍の志願兵となり、頭部に重傷を受けつつも戦い抜いた。戦後はジャーナリストとして活躍し、のちに「悪魔の辞典」に結実する辛辣なコラムを新聞・雑誌に発表する。作家としては、戦争文学のほか怪奇幻想小説も得意とし、その鋭い皮肉と冴えを高く評価した芥川龍之介は、怪奇小説「月明かりの道」の影響下に有名な「藪の中」を執筆している。70歳を過ぎて、南北戦争の古蹟をめぐる旅の途中、訪れたメキシコで謎の失踪を遂げ、現在なおその真相は明らかになっていない。
ビアスの戦争文学では、「アウルクリーク橋の出来事」が出来ばえ、知名度ともに傑出しており、「チカモーガ」「レサカにて戦死」「空駆ける騎兵」などがそれに次ぐ。「チカモーガ」は、ビアスの怪奇趣味と、戦争の悲劇を淡々と描くリアリズムが存分に発揮され、個人的に好きな作品の一つである。そのほかもいずれ劣らぬ粒ぞろいなのだが、隠れた名作を紹介するという趣旨から、ここでは「コールター・ノッチの戦い」を取上げたい。こちらも近年、電子出版専門のBOOKS桜鈴堂から新訳が発表され、長年の入手困難が一気に解消された(ただし2021年2月現在、いくつかの誤訳が残ることには注意)。

イラスト:楓 真知子
幕下にいるコールター大尉の有能さを誇った大佐にあてつけるようにして、師団長である将軍は、敵砲から恰好の標的である山上の隘路(ノッチ)へと野砲を設置するよう大尉に命ずる。命令を受けて苦しげな顔をした大尉は、しかし砲兵たちとともに坂道を駆上がり、一門置くのがやっとの切通しで、農場主の邸宅の庭に配備された十二門を相手に死闘を繰広げた。甚大な被害を出しながら、彼は悪鬼のごとく指揮を続けていたが、敵は本隊の撤退を守る後衛にすぎず、やがて砲撃をやめて去っていった。自軍の砲撃によって荒廃した邸宅を占拠した大佐は、その地下室にて、女と赤子の死体を抱いて沈黙するコールター大尉を目撃する。ここはほかならぬ大尉自身の家であり、二人は彼の妻子なのだった。
一読して感得されるのは、兵士に流血を強い、民間人も容赦なく巻込む戦争の惨禍と、標的が妻子の住む自宅だと知る大尉にも命令を拒ませない、軍隊という組織の非情さだろう。戦友の屍を踏みこえ、黙々と砲撃を続ける大尉たちの部隊に、兵から人間性を剝奪して機械化する戦争の冷酷さを見る読者もいるかもしれない。あるいは、大きな被害にもかかわらず、これが撤退する部隊相手の無駄な戦闘だったと判明するところに、いかにもビアスらしい皮肉も感じ取れるだろう。

「コールター・ノッチの戦い」は「よみがえる悪夢 ビアス傑作短編集」(下)所収(奥田俊介、芹川和之、猪狩博、大滝伊久男ほか訳、東京美術)。絶版だが大学図書館はじめ多くの図書館で所蔵されている
だが、名手ビアスによる仕掛けはそれだけではない。
なぜか歩兵による掩護射撃を禁じた将軍に不審を抱いた副将は、戦闘の最中、大佐にこんな噂を告げていた。将軍は昨夏、数週間にわたって師団をコールター邸の近くで野営させていた時、どうやら大尉の妻と何かがあり、揉めごとにまで発展したらしい。詳しくは不明ながら、司令部に何らかの苦情が入ったもようで、それで将軍はこの師団に転属させられた。その後、これも経緯は不明だが、大尉の隊が将軍の師団に配属されることになったというのだ。
副将が語るのはそれだけで、大尉夫妻と将軍との関係や、詳しいなりゆきなどはよくわからない。だが、どうやら将軍は、配下に入ったコールター大尉をあえて死地に追いやり、しかも敵砲の陣取る邸宅が大尉自身の家だと知って砲撃させたようなのだ。彼は戦闘にかこつけ、大尉を抹殺しようとしていたのか? また、同時に大尉の妻のほうも砲撃に巻込み、死を期待していたのだろうか? 自邸を砲撃させるという残酷な命令の裏に、大尉へのどんな思いがあったのか? 一方で大尉は、将軍と妻との間の出来事を知っていたのだろうか? 何も知らず、まんまと将軍の企みに乗せられただけだったのか、それとも…!? 事態は、北軍に加わった大尉と、熱烈な南部独立派だった妻という主義の対立も加わり、実はきわめて複雑な様相を帯びていたのである。
何度も読み、考えさせられたあげく、おぼろげに見える裏側の物語にぞっとさせられる。さすが芥川が好むだけあって、ビアスの辛辣さはやはり超一級なのだ。(つづく)